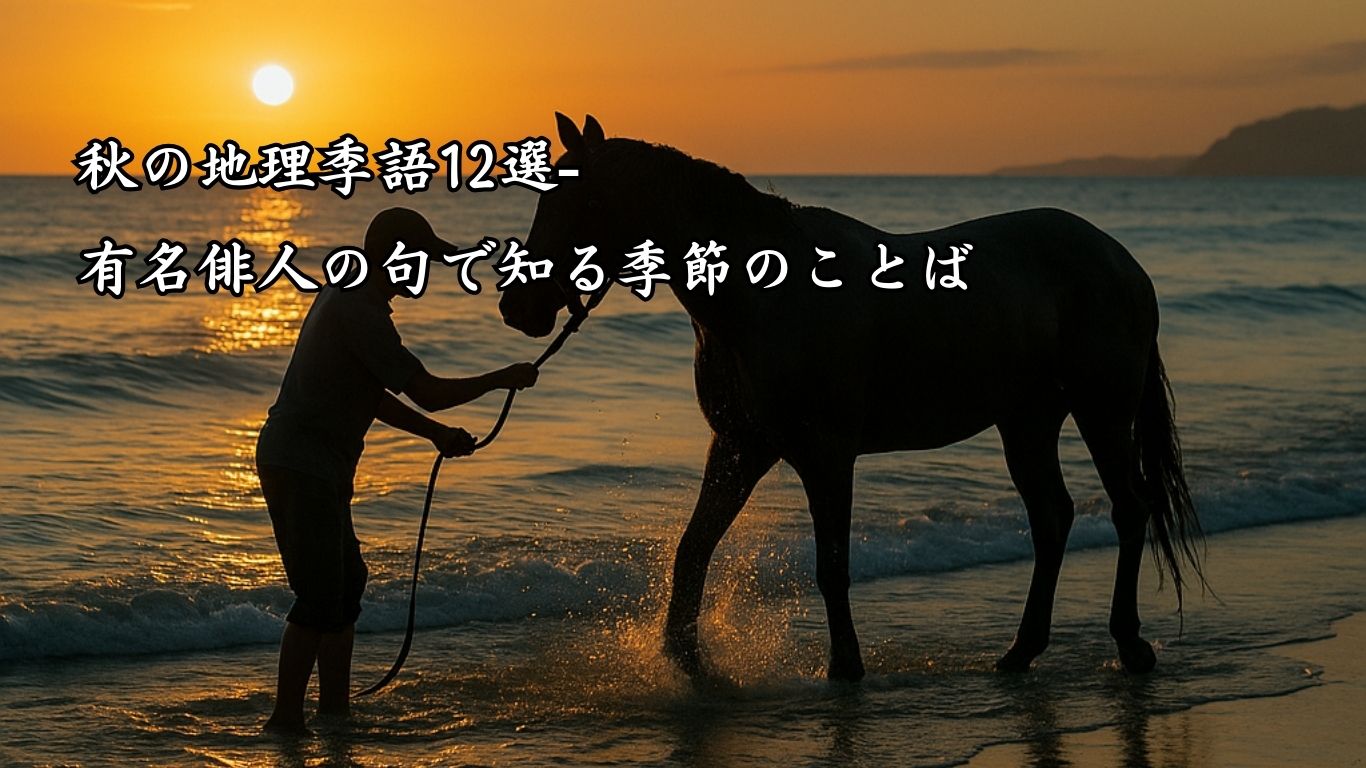秋に触れる、やさしい季語たち
秋の山や川、野や里の風景は、
俳句の中で豊かな表情を見せます。
今回は「秋の地理季語」から
代表的な12語をご紹介。
有名俳人の句とともに、
景色に映る季節の彩りを
やさしく味わってみましょう。
秋の地理季語12選
季語『秋の水』
『秋の水』の意味
秋に見られる水は、
夏の濁りが去って澄みわたり、
清らかさを増すのが特徴です。
川や池、田の水面などに
秋空が映り込み、
静けさや涼しさを漂わせます。
透明感を象徴する
秋の地理季語です。
『秋の水』のコラム
俳句では、水の澄明さや
その静けさを強調する表現に
「秋の水」がよく使われます。
夏の勢いある水流と異なり、
落ち着いた光や影を映す姿は、
人生の静かな余情とも重ねられ、
古今の句に広く詠まれています。
『秋の水』の例句をご紹介
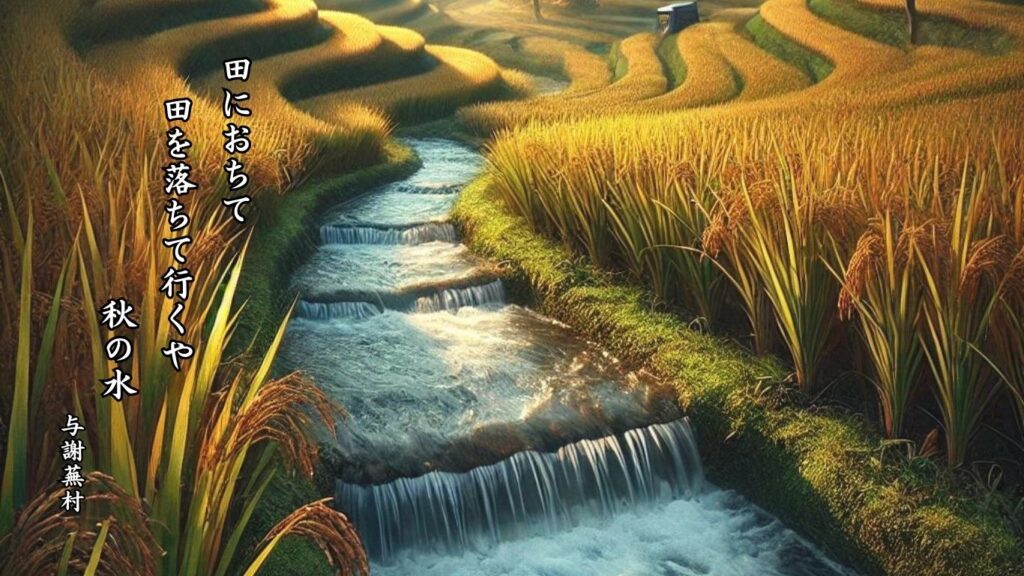
俳句:田におちて 田を落ちて行くや 秋の水
読み:たにおちて たをおちてゆくや あきのみず
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:田に落ちた水が、
さらに田を伝い流れていく。
秋の水の澄んだ流れと、
農村の景が重なり、
静かな時間の広がりを
感じさせる一句です。
季語『秋の山』
『秋の山』の意味
秋の山は、紅葉や澄んだ空気に包まれ、
四季の中でも最も鮮やかな彩りを見せます。
木々の葉が赤や黄に染まり、
山全体が静かな美をたたえる姿は、
秋を象徴する風景として
多くの俳句に詠まれます。
『秋の山』のコラム
俳句では「秋の山」は、
色彩の変化や澄んだ気配を描く題材です。
雄大な景観として詠まれる一方で、
山路や村里の生活とともに
親しみ深く描かれることも多いです。
自然の豊かさを映す
定番の季語です。
『秋の山』の例句をご紹介

俳句:信濃路や どこ迄つづく 秋の山
読み:しなのじや どこまでつづく あきのやま
俳人名:正岡子規 (まさおか しき)
→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと
要約:信濃路に果てしなく連なる秋の山々。
紅葉や澄んだ空気が景色を彩り、
雄大な自然の広がりと旅情を
感じさせます。
季語『秋の田』
『秋の田』の意味
「秋の田」とは、稲穂が実り
黄金色に広がる田を指します。
収穫期を迎えた田は、
農村の豊かさと喜びを象徴し、
秋の自然の恵みとともに
人々の暮らしを支える
代表的な地理季語です。
『秋の田』のコラム
俳句では「秋の田」は、
夕暮れや祭り、鳥居などと重ね、
農村の生活と結びつけて詠まれます。
黄金色の風景は壮大で、
実りの感謝と同時に、
秋の深まりや人の営みを
感じさせる題材です。
『秋の田』の例句をご紹介
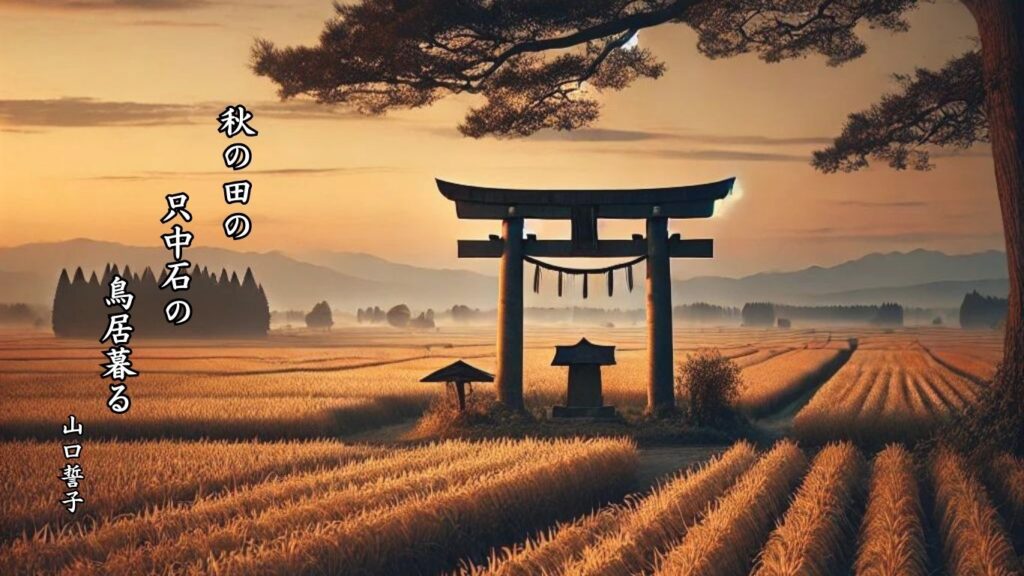
俳句:秋の田の 只中石の 鳥居暮る
読み:あきのたの ただなかいしの とりいくる
俳人名:山口誓子 (やまぐち せいし)
→ことばあそびの詩唄で誓子の句をもっと
要約:秋の田の真ん中に立つ石の鳥居が、
夕暮れの光に包まれる情景。
田園の広がりと静けさの中に、
神聖さと秋の深まりを
感じさせる一句です。
季語『秋の潮』
『秋の潮』の意味
秋の海に寄せ引く潮を「秋の潮」と
いいます。
夏の勢いある潮に比べて落ち着き、
澄んだ空や風と調和して
穏やかな趣を見せるのが特徴です。
海辺の静けさを映す
秋ならではの季語です。
『秋の潮』のコラム
俳句では「秋の潮」は、
浜辺や漁村の暮らしとともに
詠まれることが多いです。
漂う舟や寄せる波の音など、
ゆるやかな情景を描き、
人の心の静けさや余情を
重ねる表現として親しまれます。
『秋の潮』の例句をご紹介
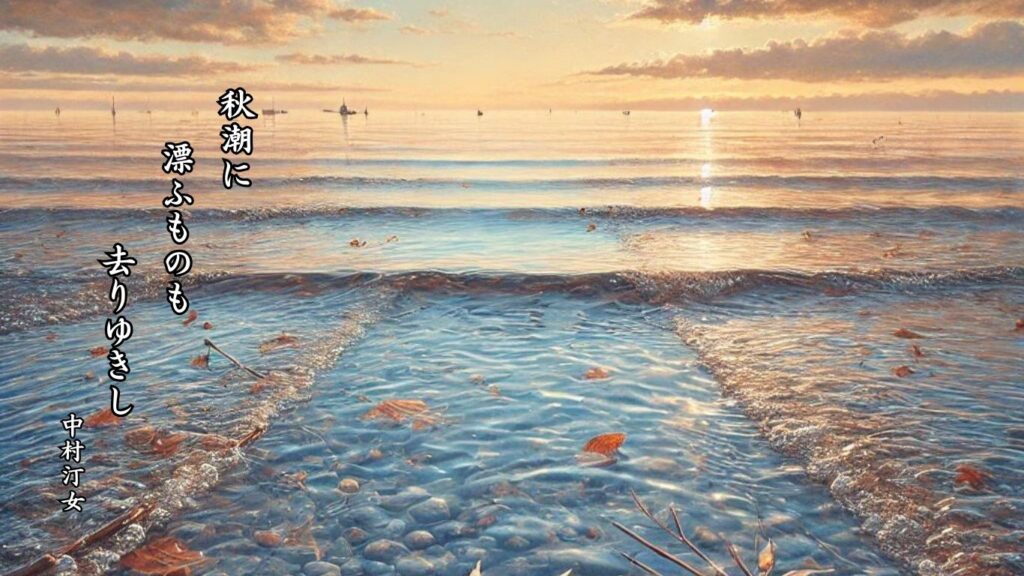
俳句:秋潮に 漂ふものも 去りゆきし
読み:あきしおに ただようものも さりゆきし
俳人名:中村汀女 (なかむら ていじょ)
→ことばあそびの詩唄で汀女の句をもっと
要約:秋の潮に浮かんでいたものが、
やがて流され去っていく。
海の静かな動きに、
季節の移ろいと人生の無常を重ね、
余情深く表現した一句です。
季語『秋の野』
『秋の野』の意味
秋草が咲き、虫の声が響く
広々とした野を「秋の野」といいます。
春の野の華やかさに比べ、
秋の野は静けさと寂しさを帯び、
広がる景色に心の余情を映す
代表的な地理季語です。
『秋の野』のコラム
俳句では「秋の野」は、
萩や薄など秋草と組み合わせて詠まれます。
夕暮れや月明かりと重なることで、
寂寥感や郷愁が深まり、
古くから和歌や俳句に親しまれる
情緒ある季語です。
『秋の野』の例句をご紹介
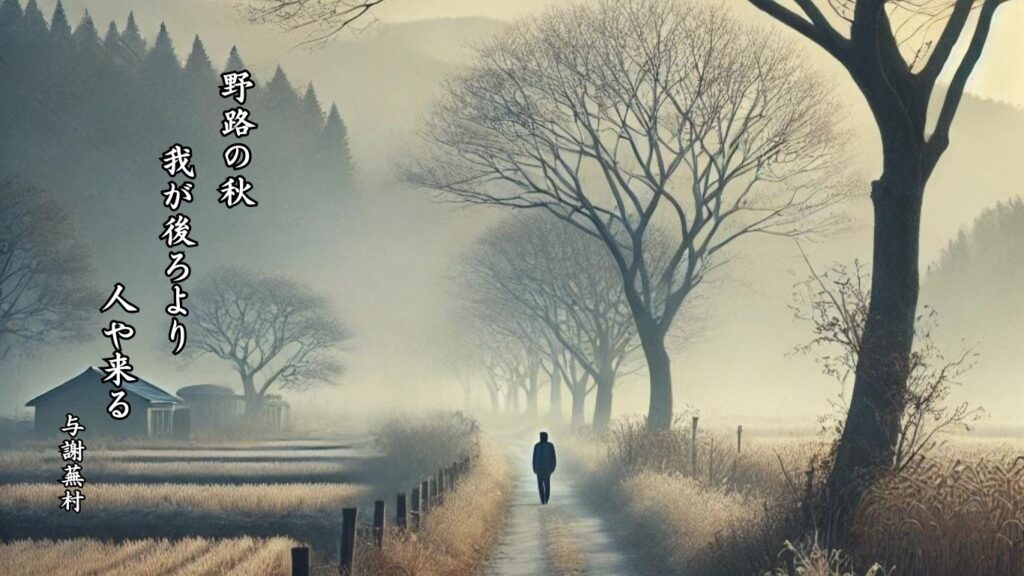
俳句:野路の秋 我が後ろより 人や来る
読み:のじのあき わがうしろより ひとやくる
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:秋の野路を歩いていると、
背後から人の気配がふと伝わる。
静かな自然の中に差し込む
人の存在が余情を生み、
秋の寂しさと人恋しさを
巧みにとらえた一句です。
季語『秋出水』
『秋出水』の意味
「秋出水」とは、秋の長雨や台風で
川が増水することをいいます。
夏の豪雨に比べ落ち着きはあるが、
水量は多く、
農作物や人々の暮らしに影響を及ぼす
自然現象を表す季語です。
『秋出水』のコラム
俳句では「秋出水」は、
自然の力強さや移ろいを
象徴する題材です。
柵や岸辺に立つ人々の姿と
組み合わせて詠まれることで、
水の勢いと人の静けさの対比が
秋ならではの風景を
印象づけます。
『秋出水』の例句をご紹介
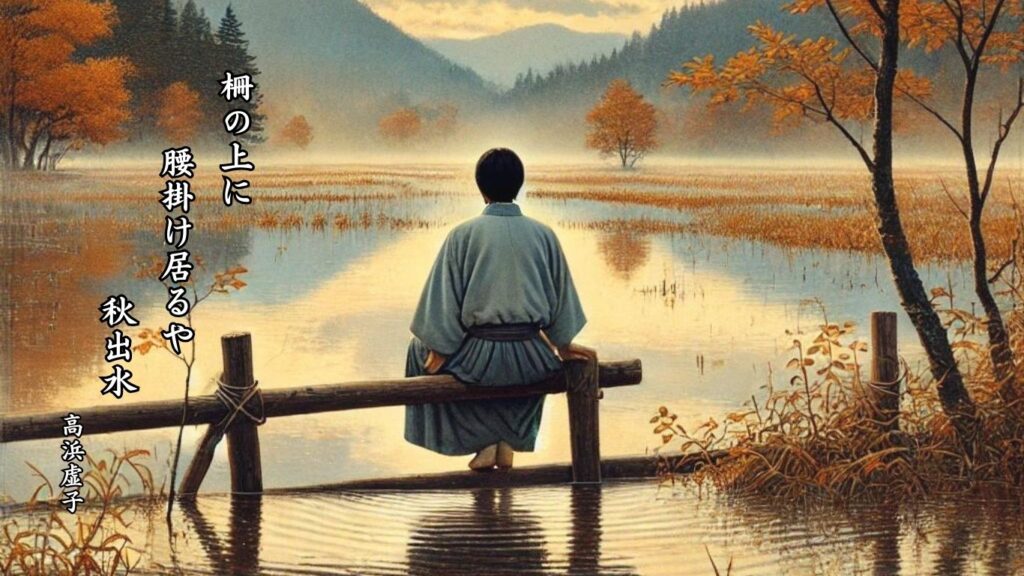
俳句:柵の上に 腰掛け居るや 秋出水
読み:さくのうえに こしかけいるや あきでみず
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:秋の出水を前に、
柵に腰を掛けて眺めている人の姿。
自然の力強さと人の静けさが重なり、
秋特有の情景と余情を
落ち着いた眼差しで切り取った一句です。
季語『秋の川』
『秋の川』の意味
秋の川は、水が澄み渡り、
夏の勢いを失って静かに流れます。
水面には澄んだ空や紅葉が映り、
季節の深まりを感じさせます。
清らかさと落ち着きを象徴する
秋の代表的な地理季語です。
『秋の川』のコラム
俳句では「秋の川」は、
澄明な水や静けさと結びつき、
旅情や余情を描く題材です。
流れる水の音や光の揺らぎに
人生を重ねる表現も多く、
静かな心象風景を映す
情緒ある季語として親しまれます。
『秋の川』の例句をご紹介
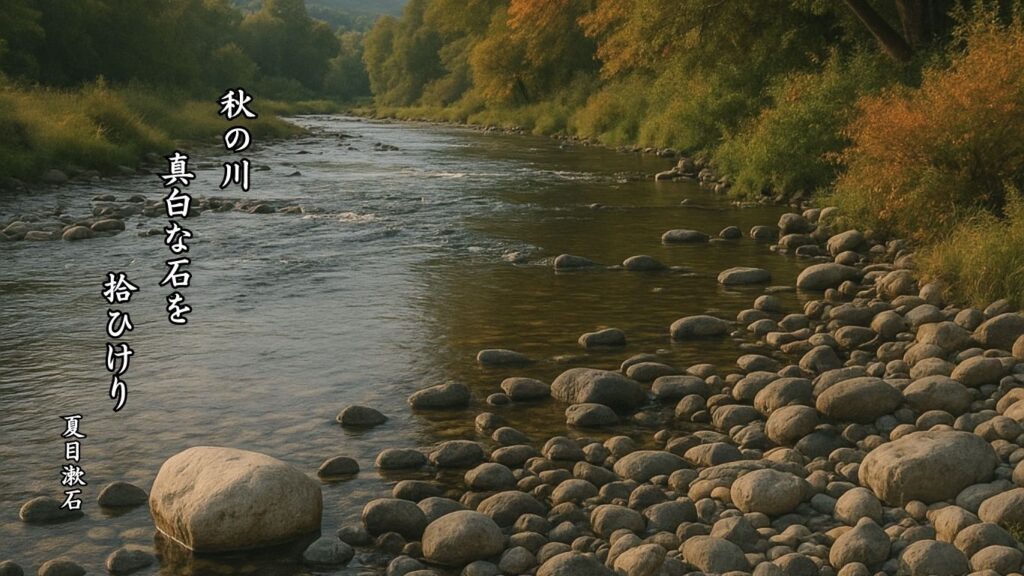
俳句:秋の川 真白な石を 拾ひけり
読み:あきのかわ ましろないしを ひろいけり
俳人名:夏目漱石 (なつめ そうせき)
要約:澄んだ秋の川で、
真っ白な石を拾う情景。
清浄な自然と素朴な行為が重なり、
秋らしい静けさと純粋さを感じさせる。
漱石らしい観察眼が光る一句です。
季語『花野』
『花野』の意味
「花野」とは、秋草の花々が
咲き広がる野原をいいます。
萩や女郎花、薄などが彩り、
秋独特の華やぎと静けさを
同時に伝えます。
自然の美しさを象徴する
代表的な秋の地理季語です。
『花野』のコラム
俳句では「花野」は、
広がる景色の雄大さと
人の心情を重ねる題材です。
果てしなく続く花野は、
郷愁や旅情を誘い、
華やかさの中に寂しさを漂わせる
情緒豊かな季語として
古くから愛されています。
『花野』の例句をご紹介
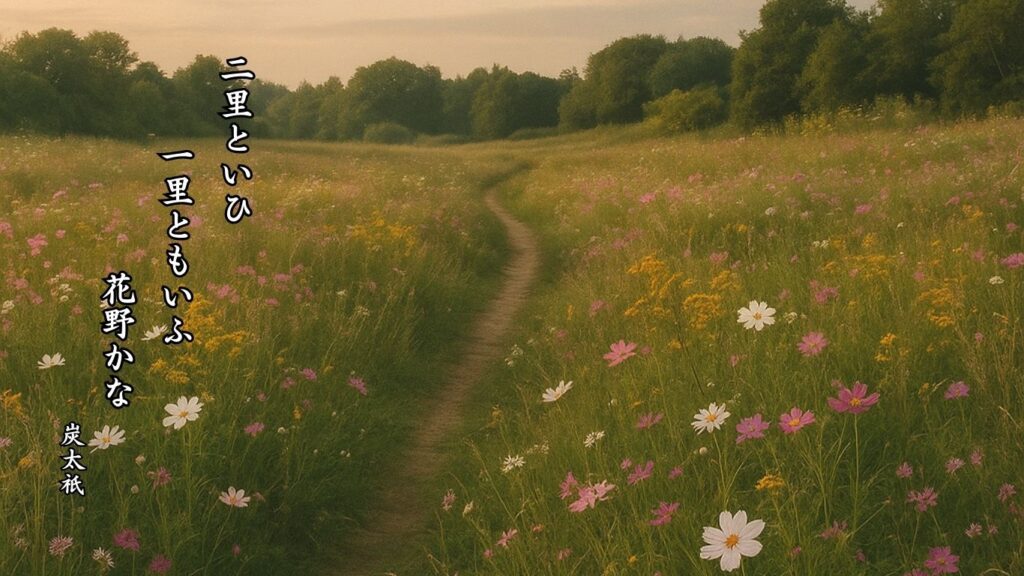
俳句:二里といひ 一里ともいふ 花野かな
読み:にりといい いちりともいう はなのかな
俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)
→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと
要約:一里とも二里ともいわれるほどに、
果てしなく広がる花野の景色。
人々の感覚を超える大自然の広がりと、
秋の花野の豊かさを
ユーモラスに描いた一句です。
季語『刈田』
『刈田』の意味
稲刈りを終えた後の田を
「刈田」といいます。
稲穂がなくなった田には、
切株が規則正しく残り、
収穫の余韻とともに
秋の農村の静かな風景を
象徴する季語です。
『刈田』のコラム
俳句では「刈田」は、
豊作の感謝や農村の営みを
映す題材として好まれます。
寂しさや落ち着きの中に、
季節の移ろいや人の営みを
感じさせ、
秋の里山を象徴する
情景として詠まれます。
『刈田』の例句をご紹介

俳句:去るほどに うちひらきたる 刈田かな
読み:さるほどに うちひらきたる かりたかな
俳人名:上島鬼貫 (うえじま おにつら)
要約:歩みを進めるほどに、
刈り終えた田が広がっていく。
収穫を終えた土地の静けさと、
開放的な広がりが重なり、
農村の秋の風景を雄大にとらえた
一句です。
季語『穭田』
『穭田』の意味
稲刈りを終えた後の田に、
切株から芽吹いた稲を
「穭(ひつじ)」といいます。
その稲が一面に生えた田を
「穭田」と呼び、
再生の力と農村の季節感を
表す秋の地理季語です。
『穭田』のコラム
俳句では「穭田」は、
収穫を終えた田に
なお芽吹く命の象徴として
詠まれます。
『穭田』の例句をご紹介
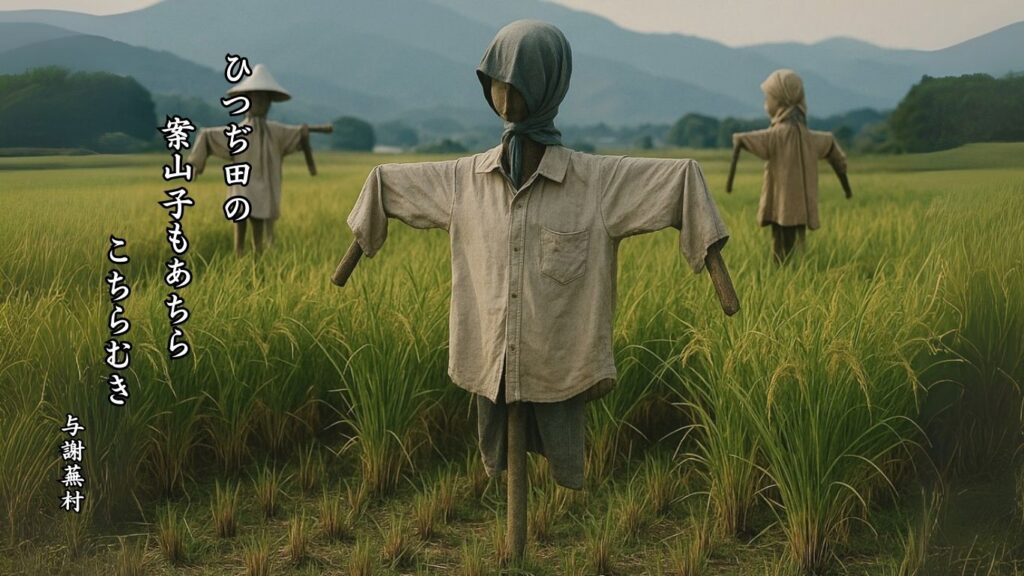
俳句:ひつぢ田の 案山子もあちら こちらむき
読み:ひつぢだの かかしもあちら こちらむき
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:刈り取った田に立つ案山子が、
あちらこちらを向いている。
農村の収穫後ののどかさと、
素朴な風景の中に漂うユーモアを
巧みにとらえた一句です。
季語『秋の海』
『秋の海』の意味
「秋の海」とは、夏の喧騒が過ぎ、
静けさを取り戻した秋の海を
指します。
穏やかな波と澄んだ空気が
広がり、人々の暮らしや心に
落ち着きを与える
秋の地理季語です。
『秋の海』のコラム
俳句では「秋の海」は、
夕陽や漁村の生活と重ねられ、
静謐な趣を表します。
夏の勢いを失い、
穏やかに広がる海は、
人生の余情や郷愁を
感じさせる題材として
多くの句に詠まれます。
『秋の海』の例句をご紹介

俳句:夕陽に 馬洗ひけり 秋の海
読み:せきように うまあらいけり あきのうみ
俳人名:正岡子規 (まさおか しき)
→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと
要約:秋の海で、夕陽を浴びながら
馬を洗う情景。
赤く沈む光と水面の輝きが重なり、
人と自然の営みを穏やかに映す。
秋の海の静けさと生活の一幕が
調和した一句です。
季語『山粧う』
『山粧う』の意味
「山粧う」とは、紅葉に彩られた
秋の山の姿を表す季語です。
木々が赤や黄に染まり、
山全体が華やかに装うように
見えることから、
自然の美を称える言葉として
俳句や和歌に親しまれています。
『山粧う』のコラム
俳句では「山粧う」は、
秋の盛りを象徴する題材です。
鮮やかな紅葉の彩りを、
衣に例えることで、
山が自らを美しく飾るかのように
表現されています。
秋景色を最も華やかに描く
季語の一つです。
『山粧う』の例句をご紹介
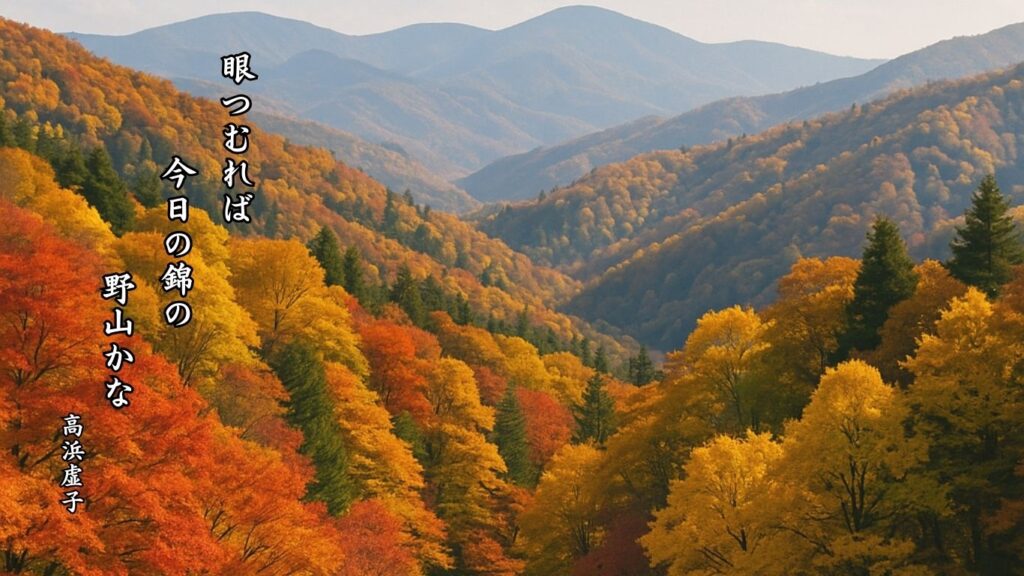
俳句:眼つむれば 今日の錦の 野山かな
読み:めつむれば けふのにしきの のやまかな
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:目を閉じてもなお、
錦のような紅葉の山野の景色が
鮮やかに浮かぶ。
自然の美が心に深く刻まれ、
秋の盛りを余情豊かに伝える、
虚子らしい印象的な一句です。
まとめ
秋の地理季語は、山や野、
川や海の自然を映し出し、
季節の移ろいを鮮やかに伝えます。
俳人たちの句にふれながら、
風景の中に潜む余情を味わい、
秋の豊かな情緒を
感じ取ってみてください。
関連リンク
📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)
🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る
🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら