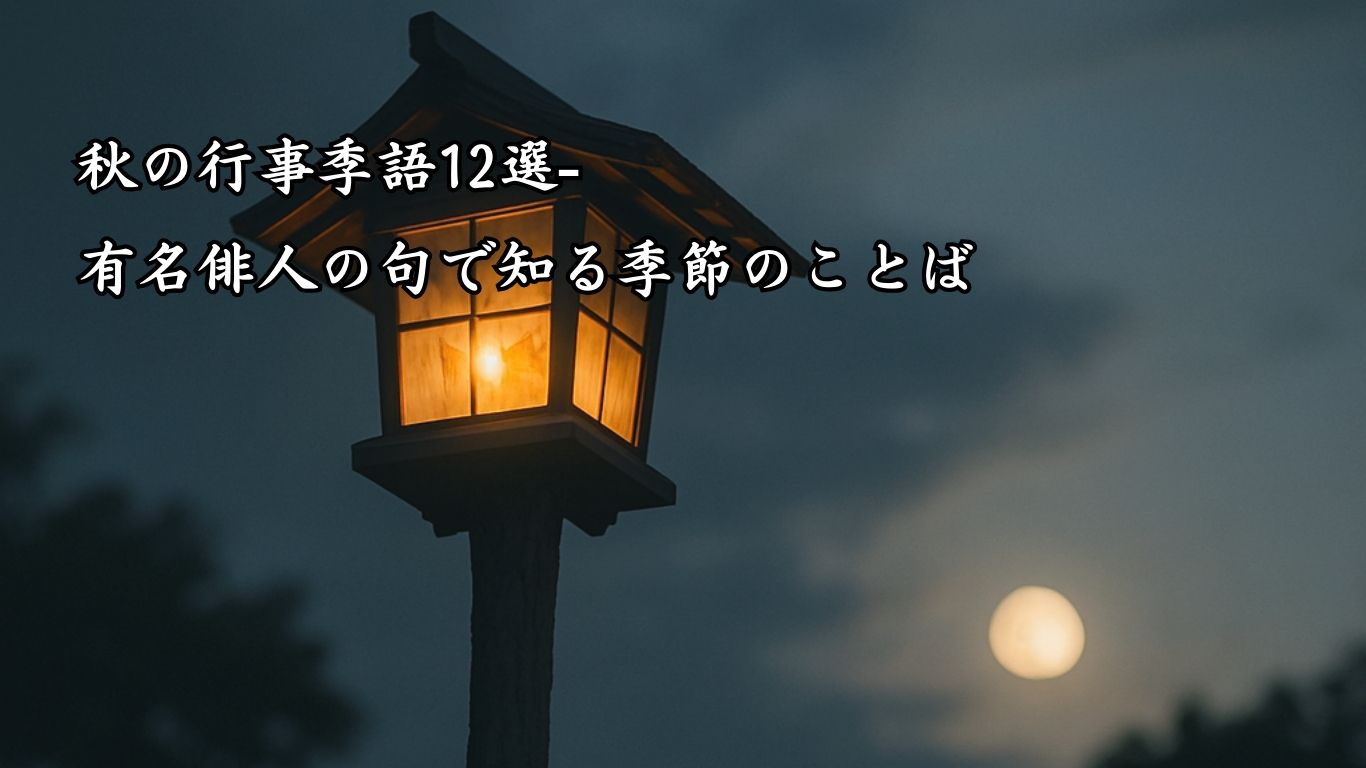秋に触れる、やさしい季語たち
秋は墓参りや星祭など、
暮らしを彩る行事が盛んに行われます。
今回は「秋の行事季語」から
代表的な12語をご紹介。
有名俳人の句を添えて、
日本の伝統と季節の彩りを
やさしく味わってみましょう。
秋の行事季語12選
季語『迎火』
『迎火』の意味
「迎火」とは、盆の入りに
祖霊を迎えるために焚く火をいいます。
家の門口や道端で火をともすことで、
先祖の霊が迷わず戻れるように祈る、
日本の伝統的な習わしを
表す行事季語です。
『迎火』のコラム
俳句では「迎火」は、
灯火の揺らめきや人々の祈りと
結びつけて詠まれます。
夕暮れや夜の情景に映える火は、
先祖を迎える荘厳さとともに、
家族のつながりや
郷愁を伝える題材として
親しまれています。
『迎火』の例句をご紹介
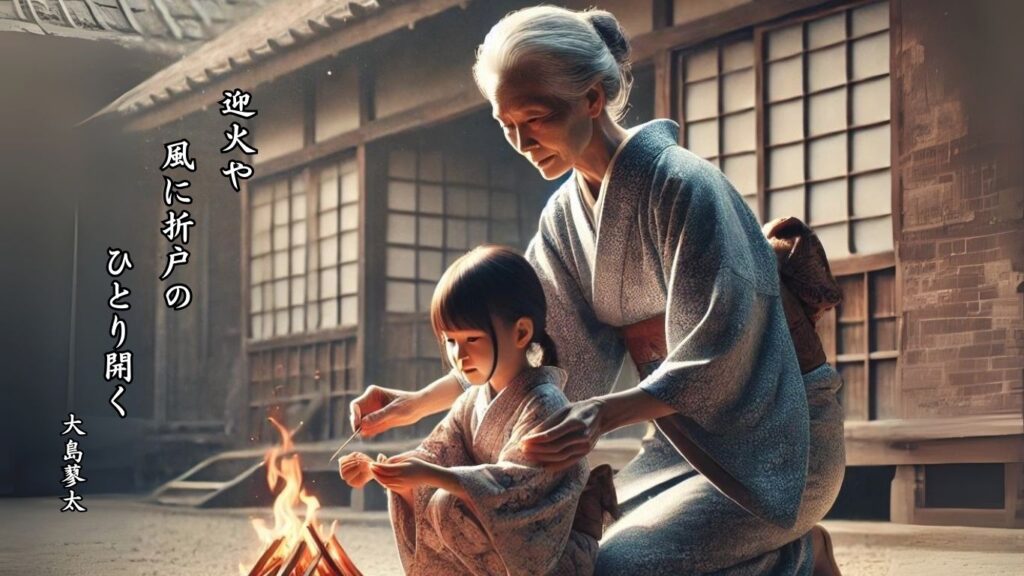
俳句:迎火や 風に折戸の ひとり開く
読み:むかえびや かぜにおりどの ひとりあく
俳人名:大島蓼太 (おおしま りょうた)
要約:迎火が焚かれる中、
風に吹かれて
折戸がひとりでに開く。
火と風、そして霊の気配が重なり、
お盆の神秘的な雰囲気を映す。
先祖を迎える心と自然が調和した
印象的な一句です。
季語『迎鐘』
『迎鐘』の意味
「迎鐘」とは、盆の入りに
先祖の霊を迎えるため撞く鐘を指します。
寺院や地域で鳴らされる鐘の音は、
祖霊が迷わず帰れるよう祈るしるし。
信仰と暮らしに根付いた
秋の行事季語です。
『迎鐘』のコラム
俳句では「迎鐘」は、
夕暮れや夜に響く鐘の音とともに
霊を迎える荘厳さを詠みます。
鐘の余韻は人々の心に染み入り、
亡き人とのつながりや郷愁を
呼び起こします。
静けさと祈りを伝える季語です。
『迎鐘』の例句をご紹介

俳句:旅人の 鳴らして行くや 迎ひ鐘
読み:たびびとの ならしてゆくや むかいがね
俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)
→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと
要約:旅人が道すがら迎鐘を鳴らしていく。
さりげない所作に、祖霊を思う祈りと
人の温かさがにじむ。
信仰と日常が自然に重なり合い、
お盆の情景を親しみ深く伝える
一茶らしい一句です。
季語『送り火』
『送り火』の意味
「送り火」とは、お盆の終わりに
祖霊を見送るために焚く火を指します。
門口や山に灯される火は、
霊を無事に送るための道しるべ。
祈りと別れを象徴する
秋の行事季語です。
『送り火』のコラム
俳句では「送り火」は、
燃えさかる炎や消えゆく火を通して
別れの情景を描きます。
夏から秋へ移る節目としても詠まれ、
祈りや郷愁、無常観を表現。
日本の伝統行事として
古くから親しまれています。
『送り火』の例句をご紹介
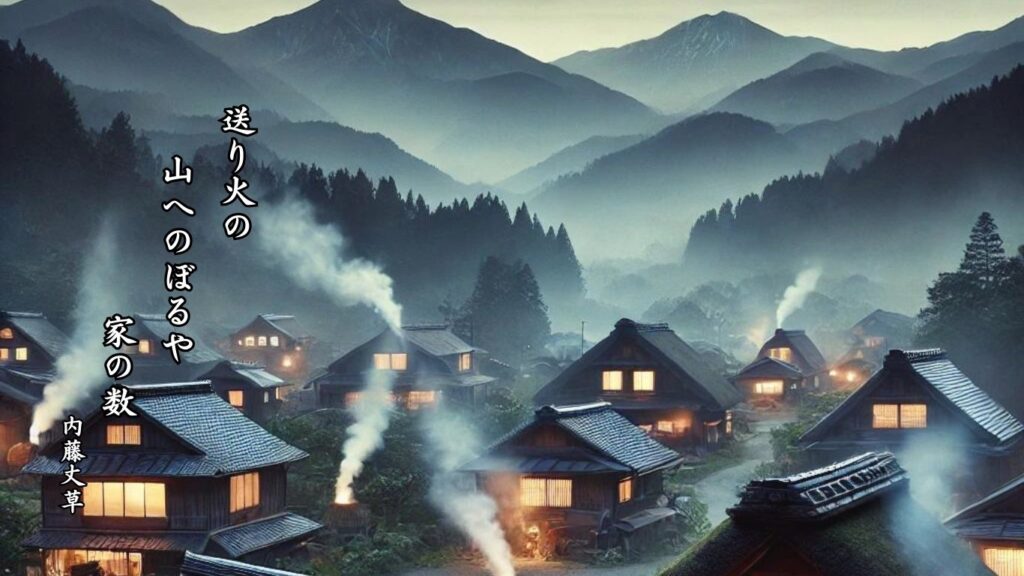
俳句:送り火の 山へのぼるや 家の数
読み:おくりびの やまへのぼるや いえのかず
俳人名:内藤丈草 (ないとう じょうそう)
→ことばあそびの詩唄で丈草の句をもっと
要約:山に昇る送り火が家の数だけ灯る。
一つ一つの火に
先祖への祈りが込められ、
夜の山を幻想的に照らす。
人々の営みと霊を送る心が重なり、
お盆の終わりの情景を
厳かに伝える一句です。
季語『大文字』
『大文字』の意味
「大文字」とは、京都の盂蘭盆会で
行われる五山送り火のひとつを指します。
山に「大」の字が炎で浮かび上がり、
祖霊を送る荘厳な行事です。
夏から秋へ移る節目を示す
代表的な行事季語です。
『大文字』のコラム
俳句では「大文字」は、
炎の壮大な光景と
送り火の意味を重ねて詠まれます。
夏の名残と秋の訪れを告げ、
人々の祈りや郷愁を映す題材です。
京都の風物詩として
古くから親しまれています。
『大文字』の例句をご紹介
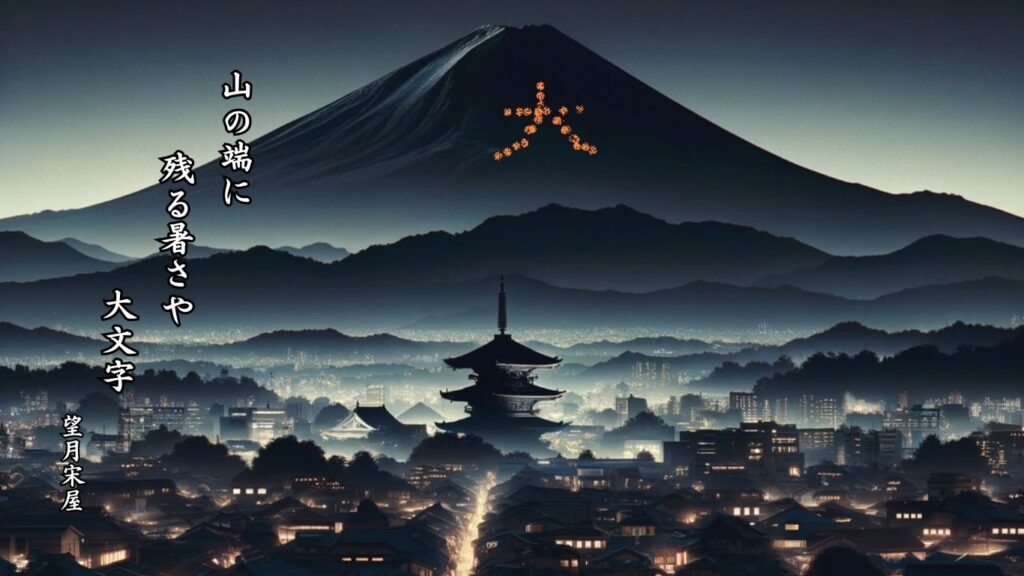
俳句:山の端に 残る暑さや 大文字
読み:やまのはに のこるあつさや だいもんじ
俳人名:望月宋屋 (もちづき そうおく)
要約:山の端に燃える大文字と、
なお残る暑さの対比を描く。
送り火の荘厳さと、
夏から秋への移ろいが重なり、
行事の迫力と季節の余情を
鮮やかに映し出した一句です。
季語『べつたら市』
『べつたら市』の意味
「べつたら市」とは、
東京・日本橋で十月に
開かれる市を指します。
大根を米麹で漬けた
「べったら漬」が名物で、
秋の収穫と商いのにぎわいを映す
行事季語です。
『べつたら市』のコラム
俳句では「べつたら市」は、
夜店の明かりや人波とともに詠まれます。
江戸の風情を伝える市は、
現代でも庶民の楽しみとして親しまれ、
秋の街の活気と郷愁を
あわせ持つ題材です。
『べつたら市』の例句をご紹介
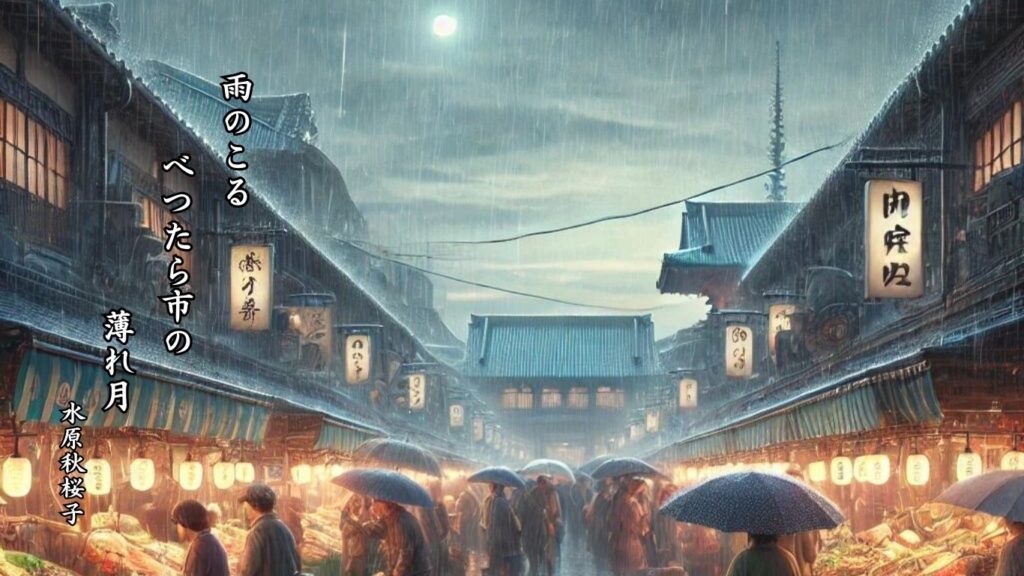
俳句:雨のこる べつたら市の 薄れ月
読み:あめのこる べつたらいちの うすれづき
俳人名:水原秋桜子 (みずはら しゅうおうし)
→ことばあそびの詩唄で秋桜子の句をもっと
要約:雨のしずくが残る市の灯りに、
薄れていく月が重なる。
人波の賑わいの裏に、
静かな秋の余情を漂わせる。
江戸情緒と季節の移ろいを
繊細に描いた秋桜子の一句です。
季語『敬老の日』
『敬老の日』の意味
「敬老の日」とは、九月の祝日で
長寿を祝い感謝を捧げる日を指します。
家庭や地域でお年寄りを敬い、
健康と長寿を願う習わしは、
秋の暮らしに根付いた
行事季語です。
『敬老の日』のコラム
俳句では「敬老の日」は、
家族の集まりや
贈り物とともに詠まれます。
古来の長寿祝いの習慣が
現代に受け継がれた行事であり、
秋の季語として、
人への感謝と絆を
象徴する題材です。
『敬老の日』の例句をご紹介

俳句:おもしろくなし 敬老の日の テレビ
読み:おもしろくなし けいろうのひの てれび
俳人名:右城暮石 (うしろ ぼせき)
要約:敬老の日のテレビ番組を見ても
面白さを感じない。
形式ばった祝いや世間の姿勢に、
寂しさや虚しさがにじむ。
現代的な視点から行事を捉え直した
暮石らしい一句です。
季語『星祭』
『星祭』の意味
「星祭」とは、七夕の行事を
指す季語です。
旧暦七月七日、秋にあたる時期に
織姫と彦星の伝説を祝います。
短冊に願いを書いて笹に飾り、
星に祈る風習は
日本各地に伝わる
秋の行事季語です。
『星祭』のコラム
俳句では「星祭」は、
夜空の星や笹飾りとともに詠まれます。
願いや祈りを込めた風習は、
家庭や地域の温かさを伝えます。
夏の印象が強いが、
俳句では秋の季語として
大切に用いられています。
『星祭』の例句をご紹介
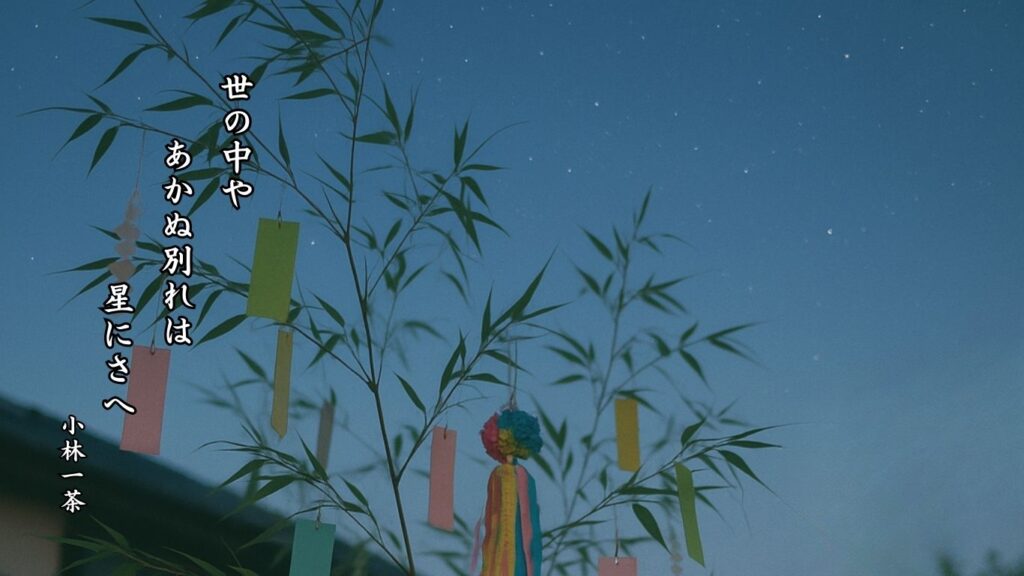
俳句:世の中や あかぬ別れは 星にさへ
読み:よのなかや あかぬわかれは ほしにさえ
俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)
→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと
要約:この世は別れの尽きぬもの、
七夕の星の逢瀬でさえ別れがある。
儚さを宇宙的な視点で捉え、
人生の哀しみを重ねた一句。
一茶らしい人間味と
哀愁を帯びた星祭の情景です。
季語『燈籠』
『燈籠』の意味
「燈籠」とは、木や石、
紙などで作られ、
灯火をともす器具を指します。
寺院や町の祭礼、
盆の供養に用いられ、
人々の祈りや行事に
欠かせないもの。
秋の夜を照らす象徴的な
行事季語です。
『燈籠』のコラム
俳句では「燈籠」は、
祭りの夜の賑わいや
供養の静けさを映す題材です。
揺れる灯りは人の心を照らし、
祈りや郷愁を感じさせます。
秋の行事と結びつき、
暮らしに光を添える
親しみ深い季語です。
『燈籠』の例句をご紹介
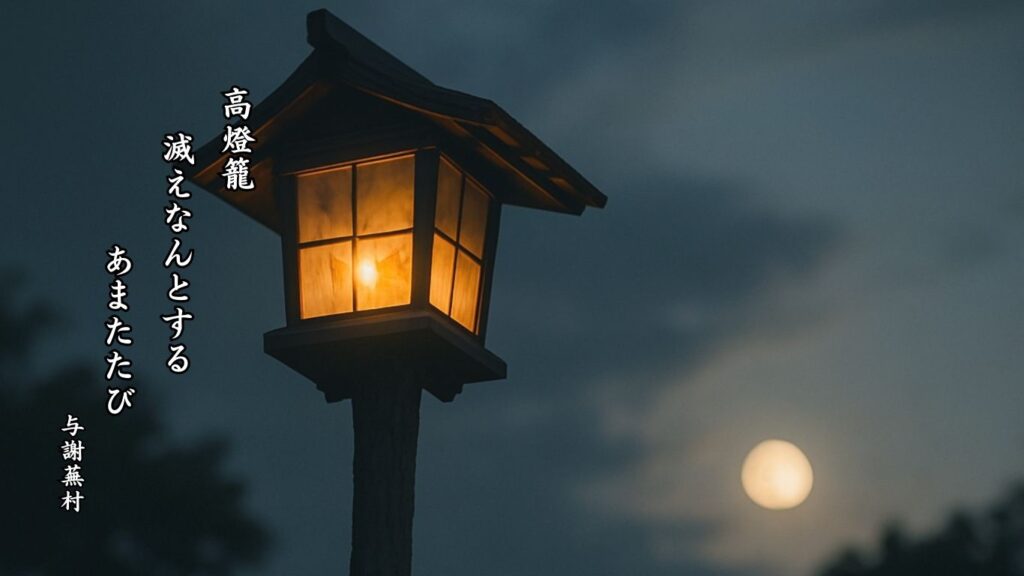
俳句:高燈籠 滅えなんとする あまたたび
読み:たかとうろう きえなんとする あまたたび
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:高く掲げられた燈籠が、
消えそうになっては幾度も持ち直す。
揺れる灯火に人の祈りと無常が重なり、
秋の夜を象徴的に照らす。
儚さと力強さを併せ持つ
蕪村らしい一句です。
季語『墓参』
『墓参』の意味
「墓参」とは、
先祖や故人の墓を訪れ、
花や供物を供えて
祈る行為をいいます。
秋の彼岸やお盆などに行われ、
先祖を敬い感謝を伝える
日本の暮らしに根付いた
行事季語です。
『墓参』のコラム
俳句では「墓参」は、
墓地の静けさや祈る人々の姿と
ともに詠まれます。
秋の澄んだ空や落葉と重なり、
無常観や郷愁を漂わせます。
日常の営みと精神文化を結ぶ
味わい深い題材です。
『墓参』の例句をご紹介
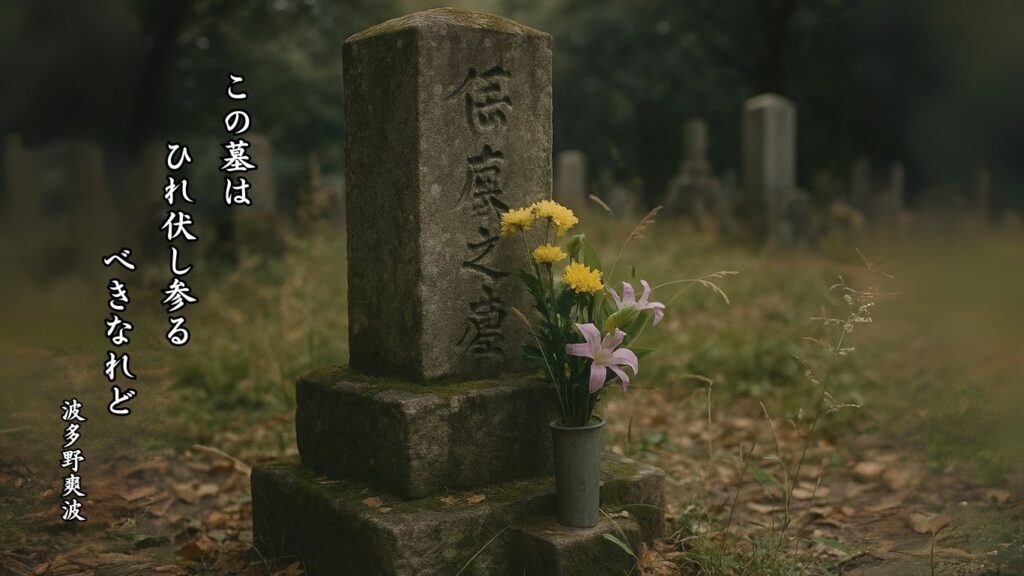
俳句:この墓は ひれ伏し参る べきなれど
読み:このはかは ひれふしまいる べきなれど
俳人名:波多野爽波 (はたの そうは)
要約:この墓には本来
ひれ伏して参るべきだ。
しかしそうしきれない
自分の思いがある。
墓参という行為に
向き合う心の揺れを映し、
先祖や故人への敬意と
個人の感情が
交錯する一句です。
季語『中元』
『中元』の意味
「中元」とは、旧暦七月十五日に
行われる年中行事を指します。
本来は道教や仏教に由来し、
祖霊を祀る日とされました。
現代では贈答の習慣が広まり、
夏から秋にかけての
行事季語として親しまれています。
『中元』のコラム
俳句では「中元」は、
贈り物や礼状と結びついて詠まれます。
人と人との絆を確かめ合う行為は、
季節の移ろいとともに
社会的なつながりを感じさせます。
古来の宗教行事と
現代の習俗が交差する
特徴的な季語です。
『中元』の例句をご紹介
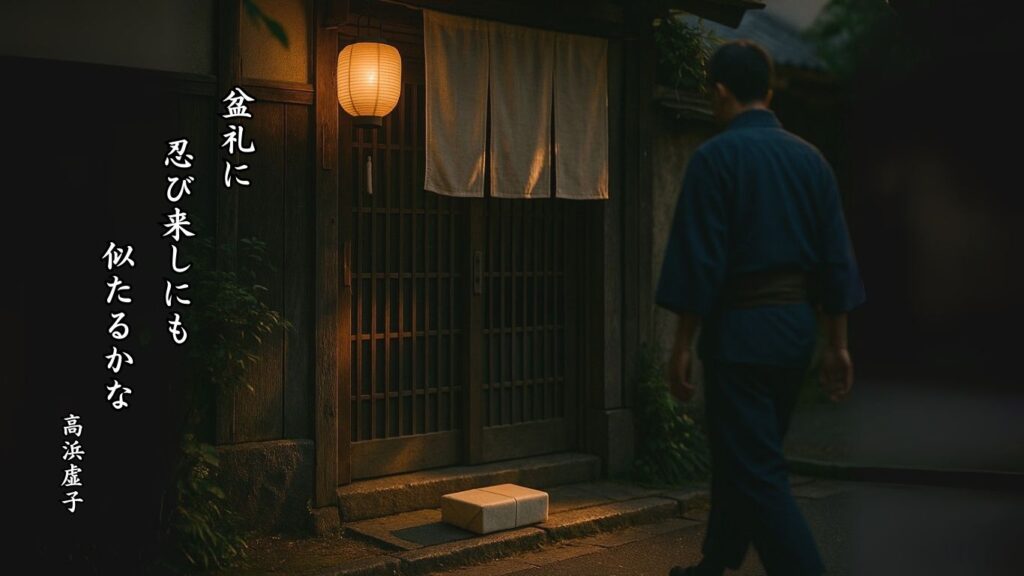
俳句:盆礼に 忍び来しにも 似たるかな
読み:ぼんれいに しのびきしにも にたるかな
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:中元の贈り物が届くさまを、
ひそやかに訪れる
姿に重ねている。
人と人との礼を交わす習慣に、
控えめながらも
温かな心遣いを感じさせ、
季節の行事に宿る人情を
しみじみと表した一句です。
季語『重陽』
『重陽』の意味
「重陽」とは、旧暦九月九日に
行われる五節句のひとつです。
奇数の最大数「九」が重なる日を
めでたい日とし、
菊を鑑賞したり、
菊酒を飲んで長寿を願う
行事を表す季語です。
『重陽』のコラム
俳句では「重陽」は、
菊の花や菊酒とともに詠まれます。
秋の深まりを告げる節句として、
長寿や健康を祈る心が込められます。
古くから宮中や庶民に伝わり、
秋の行事を彩る題材として
親しまれています。
『重陽』の例句をご紹介

俳句:朝露や 菊の節句は 町中も
読み:あさつゆや きくのせっくは まちなかも
俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)
→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと
要約:朝露に濡れる
清らかな景とともに、
町中が菊の節句を祝う。
自然の清々しさと
人々の行事が重なり、
長寿と健康を願う祈りが広がる。
秋の重陽を明るく映した
太祇らしい一句です。
季語『赤い羽根』
『赤い羽根』の意味
「赤い羽根」とは、秋に行われる
共同募金運動を象徴する言葉です。
寄付をした人に赤い羽根を渡す習慣は、
助け合いと連帯の心を表します。
現代社会に根付いた
秋の行事季語です。
『赤い羽根』のコラム
俳句では「赤い羽根」は、
人々の胸に飾られる小さな羽根を通し、
社会のつながりや温かさを描きます。
秋空の下で広がる募金活動は、
伝統的な季語とは異なり、
近代的な生活感を映す題材として
詠まれています。
『赤い羽根』の例句をご紹介

俳句:駅頭の 雨瀧なせり 愛の羽根
読み:えきとうの あめたきなせり あいのはね
俳人名:水原秋桜子 (みずはら しゅうおうし)
→ことばあそびの詩唄で秋桜子の句をもっと
要約:駅頭で募金活動に励む人々に、
雨が滝のように降りかかる。
胸の赤い羽根が愛の象徴となり、
困難の中にも人を思う心が輝く。
社会の営みと季語の新しさを
映した一句です。
まとめ
秋の行事季語は、祈りや祝いを通じて
人々の暮らしに季節を映します。
俳人の句を通して、
月見や祭り、供養などの行事に宿る
日本の心と秋の彩りを味わい、
伝統の深さを感じてみてください。
関連リンク
📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)
🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る
🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら