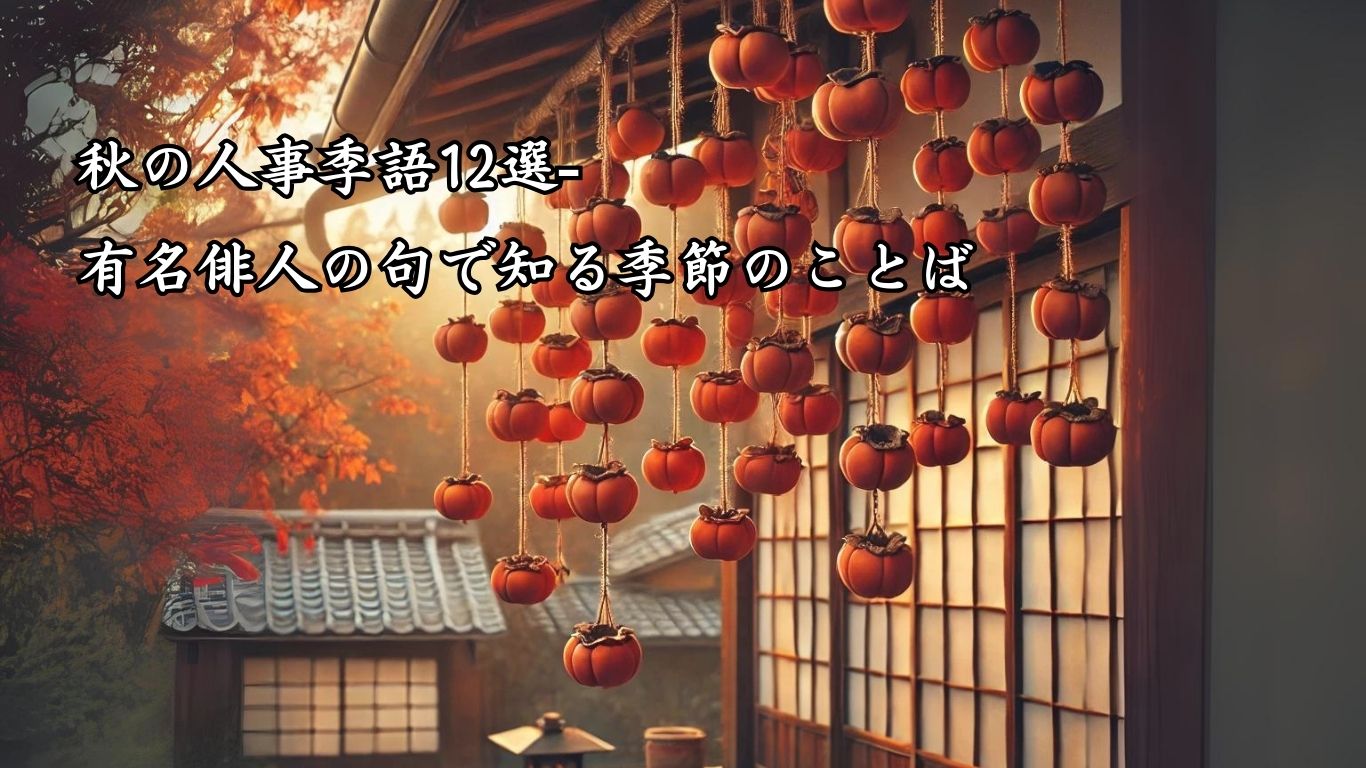秋に触れる、やさしい季語たち
秋の暮らしや行事に寄り添う言葉が、
俳句には「人事季語」として息づいています。
今回はその中から代表的な12語をご紹介。
有名俳人の句とともに、
人の営みに映る秋の彩りを
やさしく味わってみましょう。
秋の人事季語12選
季語『秋の燈』
『秋の燈』の意味
「秋の燈」とは、秋の夜にともす
灯火を指す季語です。
夏の名残が去り、
夜の時間が長くなるにつれて、
人々の暮らしに欠かせない
温かみのある光となり、
静かな秋の情緒を
映し出します。
『秋の燈』のコラム
俳句では「秋の燈」は、
家々の灯りや行灯などを通して
秋の夜の趣を表します。
涼しさや寂しさの中に
人の営みの温もりを添える表現で、
孤独や郷愁を和らげる
やさしい季語として
古くから親しまれています。
『秋の燈』の例句をご紹介
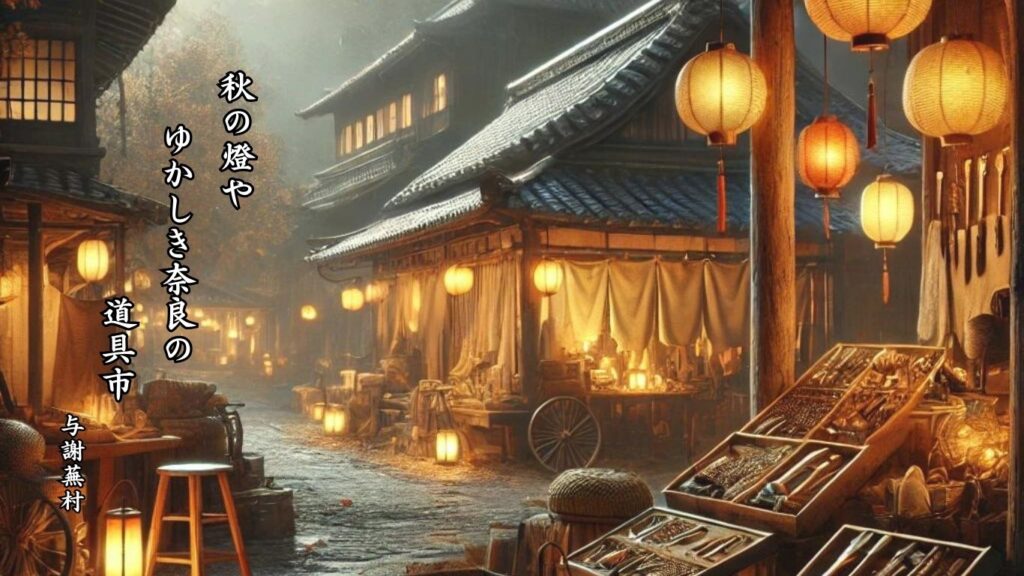
俳句:秋の燈や ゆかしき奈良の 道具市
読み:あきのひや ゆかしきならの どうぐいち
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:奈良の道具市にともる秋の灯火。
古都の風雅と人々の営みが重なり、
夜の静けさに温もりを添えています。
秋の燈が文化と暮らしを照らす、
蕪村らしい雅趣あふれる一句です。
季語『濁酒』
『濁酒』の意味
「濁酒」とは、米を発酵させた
白く濁った酒を指します。
秋祭や収穫の祝いに供され、
農村の喜びや人々の絆を
象徴する季語です。
素朴で力強い味わいが、
秋の風物として親しまれています。
『濁酒』のコラム
俳句では「濁酒」は、
祭や人の集いと結びつき、
喜びや賑わいを表現します。
一方で、孤独や侘びを
酒に託して詠む句もあり、
人の暮らしの温もりから
哀感までを映す
懐の深い季語です。
『濁酒』の例句をご紹介

俳句:山里や 杉の葉釣りて にごり酒
読み:やまざとや すぎのはつりて にごりざけ
俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)
→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと
要約:山里で杉の葉を釣り飾り、
にごり酒を楽しむ情景。
自然と人の営みが寄り添い、
素朴な暮らしの中に喜びと温もりを
感じさせる一句です。
一茶らしい庶民的な眼差しが光ります。
季語『茸飯』
『茸飯』の意味
「茸飯」とは、
秋に採れた茸を炊き込んだご飯を指します。
松茸をはじめとする山の恵みを
米とともに味わうことで、
秋の豊かな実りを象徴する
季語として親しまれています。
『茸飯』のコラム
俳句では「茸飯」は、
収穫の喜びや家庭の温もりを
映す題材として詠まれます。
香りや湯気の描写を通じて
五感に訴える表現が多く、
素朴な味覚の中に
秋の実りや人々の団らんを
感じさせる季語です。
『茸飯』の例句をご紹介

俳句:平凡な 日々のある日の きのこ飯
読み:へいぼんな ひびのあるひの きのこめし
俳人名:日野草城 (ひの そうじょう)
要約:平凡な日々の一場面に出てくる茸飯。
特別ではないからこそ、
日常の中の温かさや豊かさを感じさせる。
秋の味覚と暮らしの安らぎを重ねた、
草城らしい穏やかな一句です。
季語『栗飯』
『栗飯』の意味
「栗飯」とは、秋に実った栗を
米とともに炊き上げたご飯を指します。
ほくほくとした栗の甘みが
季節の味覚を彩り、
収穫の喜びを分かち合う
秋の食卓に欠かせない
代表的な人事季語です。
『栗飯』のコラム
俳句では「栗飯」は、
秋の実りと団らんの象徴として
多く詠まれます。
山里の素朴な暮らしや
祭りの振る舞いに登場し、
温かな家庭の情景と結びつきます。
秋の味覚を五感で伝える
親しみ深い季語です。
『栗飯』の例句をご紹介
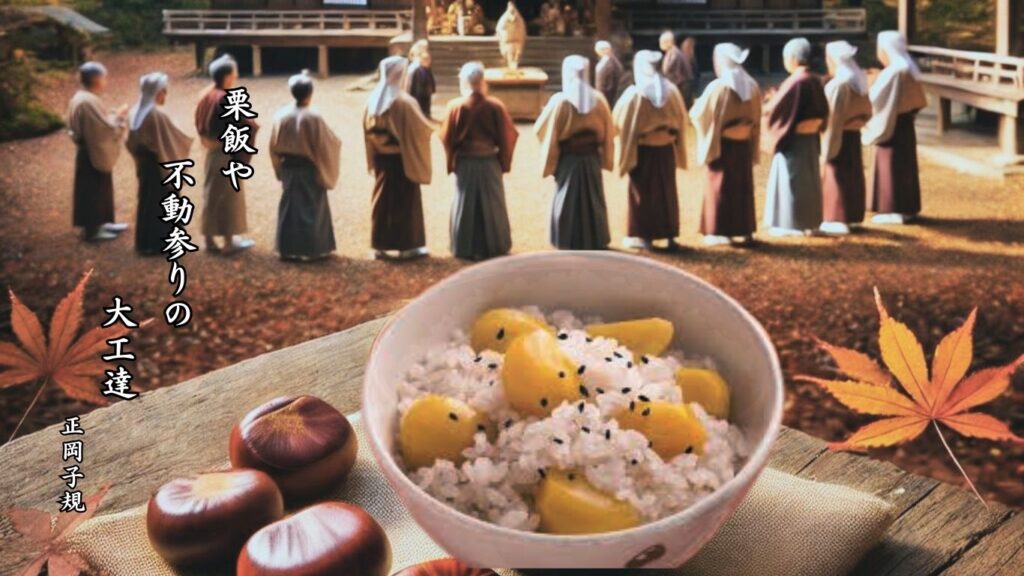
俳句:栗飯や 不動参りの 大工達
読み:くりめしや ふどうまいりの だいくたち
俳人名:正岡子規 (まさおか しき)
→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと
要約:不動参りに集う大工たちが、
栗飯を味わう情景。
信仰と仕事、そして秋の味覚が結びつき、
人々の暮らしの力強さと温もりを
鮮やかに映す一句です。
子規らしい写実が光ります。
季語『干柿』
『干柿』の意味
「干柿」とは、渋柿を皮むきして
軒先などに吊るし、乾燥させたもの。
秋の日差しと風を受けて甘みが増し、
冬の保存食として重宝されます。
秋の実りを暮らしに活かす
代表的な人事季語です。
『干柿』のコラム
俳句では「干柿」は、
軒に連なる柿の姿や
干す人々の営みとともに詠まれます。
秋の日差しや夕景と重ねることで、
郷愁や素朴な温もりを表現。
自然と人の暮らしを結ぶ
味わい深い季語です。
『干柿』の例句をご紹介
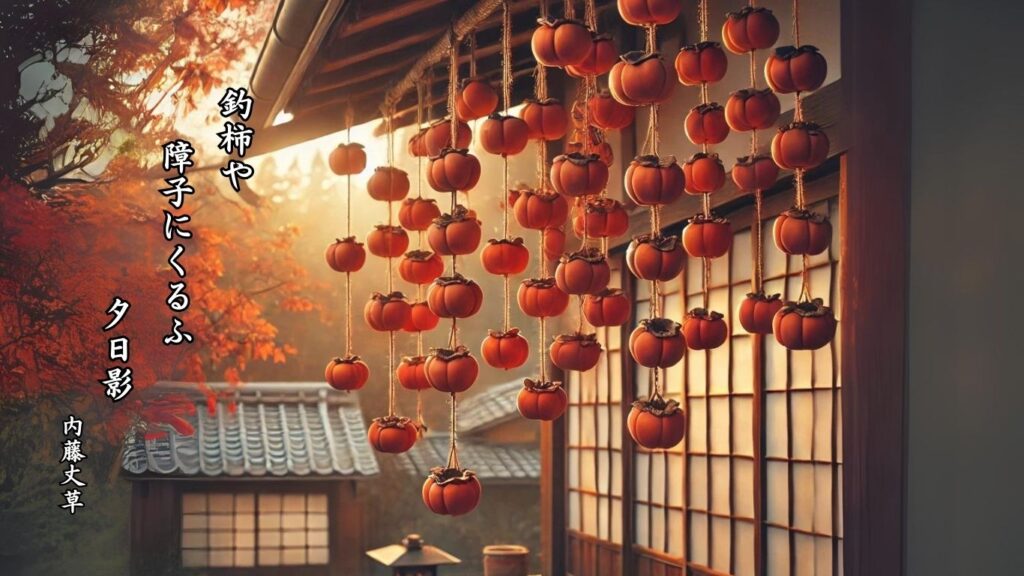
俳句:釣柿や 障子にくるふ 夕日影
読み:つりがきや しょうじにくるう ゆうひかげ
俳人名:内藤丈草 (ないとう じょうそう)
→ことばあそびの詩唄で丈草の句をもっと
要約:吊るされた柿に、夕日の影が
障子に揺らめいて映る。
素朴な暮らしの中に、
秋の日の移ろいと郷愁を感じさせる。
干柿の温もりと影の儚さが
心に余情を残す一句です。
季語『案山子』
『案山子』の意味
「案山子」とは、田畑に立てて
鳥獣を追い払う人形をいいます。
収穫期の農村に欠かせない存在で、
秋の野に静かに立つ姿は、
郷愁や孤独を感じさせる
象徴的な人事季語です。
『案山子』のコラム
俳句では「案山子」は、
秋の田や野の広がりとともに
詠まれます。
人に似た姿が孤独や寂しさを呼び、
一方で親しみ深い存在感も。
農村の風景と人の心を映す
味わい深い題材です。
『案山子』の例句をご紹介

俳句:其許は 案山子に似たる 和尚かな
読み:そこもとは かかしににたる おしょうかな
俳人名:夏目漱石 (なつめ そうせき)
要約:案山子のようにじっと立つ和尚の姿。
人形めいた静けさの中に、
どこか親しみと滑稽さがにじむ。
秋の案山子のイメージを重ねて、
人と自然の風景を味わい深く描いた
一句です。
季語『秋袷』
『秋袷』の意味
「秋袷」とは、裏地のある袷仕立ての
着物を秋に着ることをいいます。
単衣から衣替えをして、
朝夕の涼しさに備える装いです。
暮らしの中に季節を映す
人事季語として用いられます。
『秋袷』のコラム
俳句では「秋袷」は、
衣替えや季節感を表す題材です。
気候の変化に応じた装いは、
秋の始まりを象徴する生活の一面。
人々の慎ましい暮らしや、
移ろう季節への感受性を
映し出す表現です。
『秋袷』の例句をご紹介

俳句:雨の日の 客と出てたつ 秋袷
読み:あめのひの きゃくとでてたつ あきあわせ
俳人名:原石鼎 (はら せきてい)
要約:雨の日、秋袷をまとい客を送り出す。
日常の小さな所作の中に、
季節の移ろいと人の心遣いが映る。
秋の装いが生活の一場面に寄り添い、
しっとりとした余情を残す一句です。
季語『新米』
『新米』の意味
「新米」とは、その年に収穫された
新しい米を指します。
秋の実りを最も実感できる食材で、
白くつややかな炊き上がりは、
収穫の喜びと感謝を映す
暮らしの季語として
親しまれています。
『新米』のコラム
俳句では「新米」は、
実りの象徴として多く詠まれます。
香りや食感の描写を通じて、
秋の恵みと人々の喜びを伝えます。
神前への供えや祝宴など、
収穫行事と結びつけられることも多く、
生活と深く関わる季語です。
『新米』の例句をご紹介
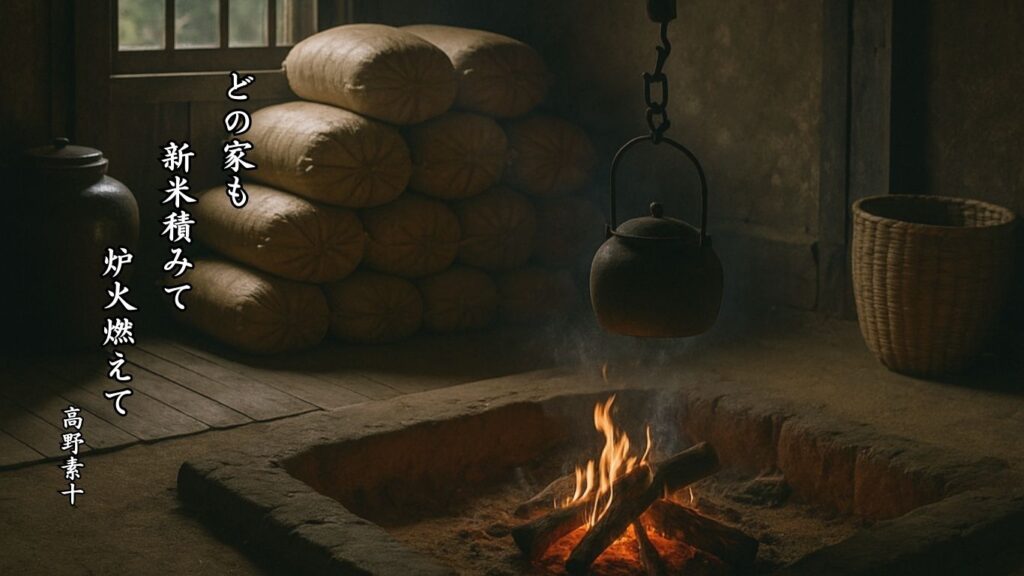
俳句:どの家も 新米積みて 炉火燃えて
読み:どのいえも しんまいつみて ろびもえて
俳人名:高野素十 (たかの すじゅう)
要約:どの家にも新米が積まれ、
炉火が燃える温かな光景。
収穫の喜びと家庭のぬくもりが重なり、
秋の恵みに感謝する暮らしが浮かぶ。
素朴で豊かな人々の営みを映した一句です。
季語『秋団扇』
『秋団扇』の意味
「秋団扇」とは、夏を越えて
秋になっても用いられる団扇を指します。
残る暑さに使われつつも、
季節の移ろいとともに
やがて不要になっていく姿に、
夏と秋の境目の感覚を
伝える季語です。
『秋団扇』のコラム
俳句では「秋団扇」は、
過ぎ去る季節の名残を象徴します。
かつて盛んに使われた団扇が
秋風の中に取り残される光景は、
静かな寂しさや余情を漂わせます。
人の暮らしと季節感を結ぶ
風雅な題材です。
『秋団扇』の例句をご紹介

俳句:秋団扇 四五本ありて 用ふなし
読み:あきうちわ しごほんありて もちうなし
俳人名:日野草城 (ひの そうじょう)
要約:数本の秋団扇がまだ手元にあるが、
もう使うことはない。
季節が移り、役目を終えた物の姿に
静かな寂しさが漂う。
人の暮らしと自然の循環を映す
余情ある一句です。
季語『稲扱』
『稲扱』の意味
「稲扱」とは、収穫した稲から
籾をしごいて落とす作業をいいます。
秋の収穫の一工程として、
農村の暮らしを象徴する言葉です。
労働の厳しさと実りの喜びを
同時に伝える人事季語です。
『稲扱』のコラム
俳句では「稲扱」は、
農作業の音や姿とともに
描かれることが多いです。
秋空の下、家族総出で行う光景は、
収穫の喜びや共同体の絆を
感じさせます。
農村の生活感を映す
季語として親しまれます。
『稲扱』の例句をご紹介
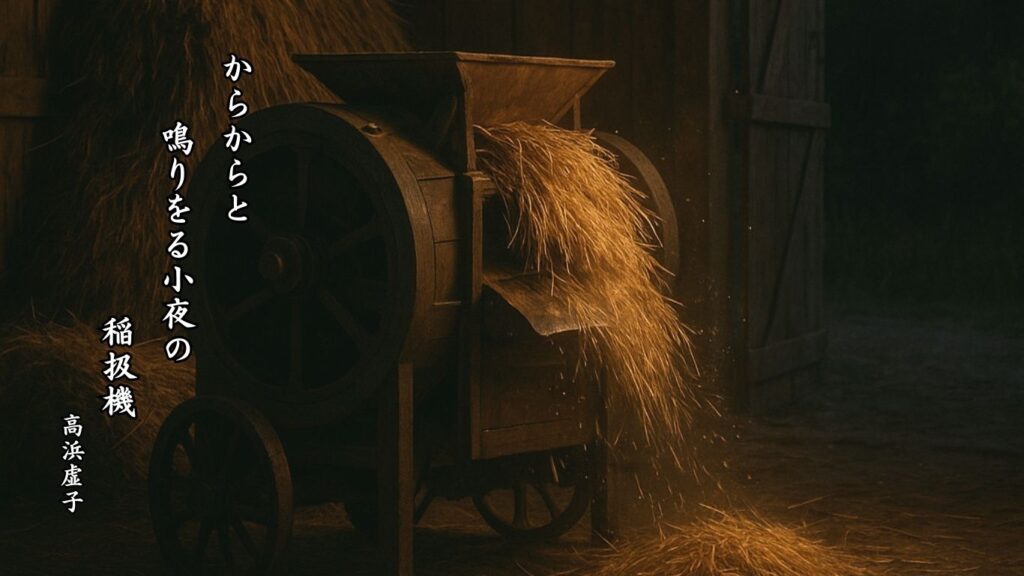
俳句:からからと 鳴りをる小夜の 稲扱機
読み:からからと なりをるさよの いねこぎき
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:小夜に「からから」と鳴る稲扱機の音。
農作業の響きが秋の静けさに溶け込み、
収穫の喜びと労働の力強さを伝える。
人と自然の営みを象徴する
情景豊かな一句です。
季語『月見』
『月見』の意味
「月見」とは、旧暦八月十五夜に
満月を鑑賞する風習をいいます。
月を眺め、団子や芒を供える行事は、
秋の豊かな収穫と自然への感謝を
表すもの。
風雅と祈りを重ねる
代表的な人事季語です。
『月見』のコラム
俳句では「月見」は、
団らんや静かな独酌の場面など、
多彩に詠まれます。
澄んだ秋空に輝く月は、
人生や自然の象徴とも重なり、
人々の心を映し出します。
古来より和歌や俳句に
多く詠まれる題材です。
『月見』の例句をご紹介
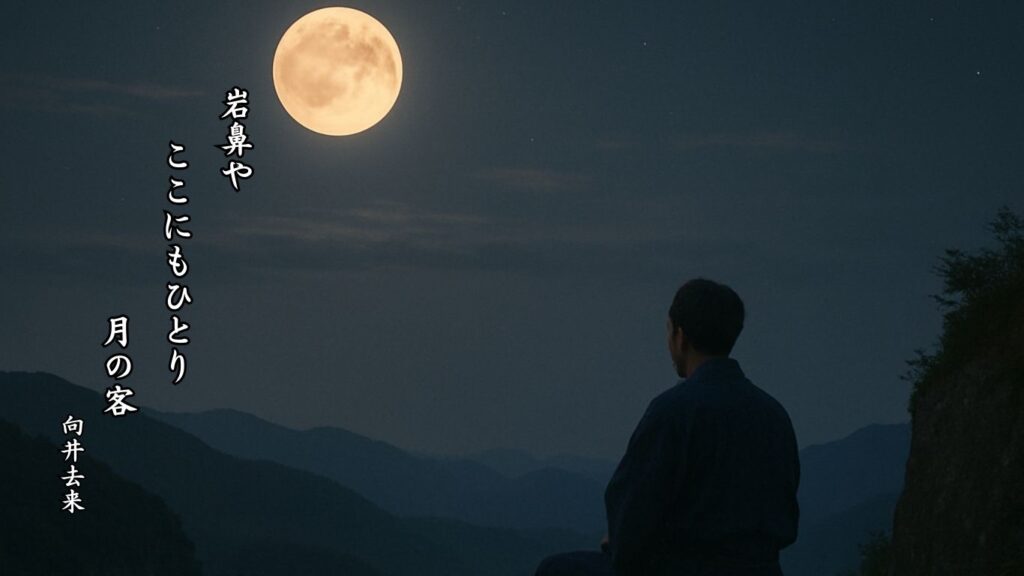
俳句:岩鼻や ここにもひとり 月の客
読み:いわはなや ここにもひとり つきのきゃく
俳人名:向井去来 (むかい きょらい)
→ことばあそびの詩唄で去来の句をもっと
要約:岩の突端に、月を眺める客がひとり。
静けさと孤独の中に、
秋の月見の風雅が広がる。
自然の景と人の心が響き合い、
孤独を超えて季節の美を味わう
余情豊かな一句です。
季語『茸狩』
『茸狩』の意味
「茸狩」とは、山や野に分け入り、
茸を探して採ることをいいます。
秋の実りを直接自然から得る営みで、
家族や仲間との行楽としても親しまれます。
山の恵みを味わう
秋の人事季語です。
『茸狩』のコラム
俳句では「茸狩」は、
茸を探す人々の姿や、
山里の風景とともに詠まれます。
豊かな自然と人との関わりを映し出し、
収穫の喜びや探す楽しさを表現。
秋の実りと人の営みを結ぶ
親しみ深い季語です。
『茸狩』の例句をご紹介

俳句:茸狩りや 頭を挙ぐれば 峰の月
読み:たけがりや こうべをあぐれば みねのつき
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:茸狩りに没頭し、ふと頭を上げると
山の峰に秋の月が輝いている。
自然の恵みを探す人の営みと、
澄んだ夜空の美しさが交わり、
秋の風景の広がりを鮮やかに描いた
蕪村らしい一句です。
まとめ
秋の人事季語は、暮らしや行事に
寄り添いながら季節を映します。
俳人の句を通じて、
食や祭り、装いの中に広がる
秋の彩りを味わうことで、
日常の中にある豊かな季節感を
感じ取ってみてください。
関連リンク
📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)
🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る
🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら