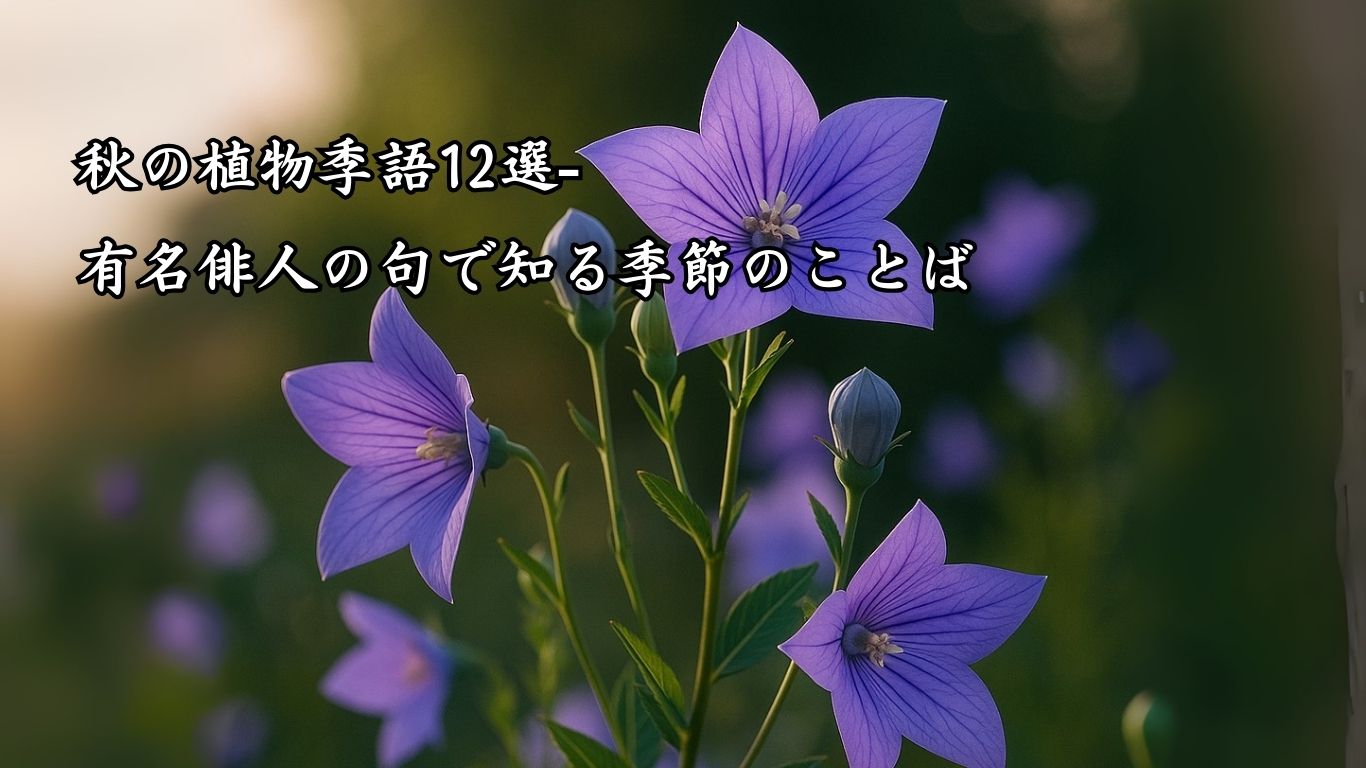秋に触れる、やさしい季語たち
秋の草花は、俳句に
深い彩りを与えてきました。
萩や芒、菊などの植物季語を、
有名俳人の句とともに紹介し、
移ろう季節の風情を
わかりやすく味わいます。
秋の植物季語12選
季語『朝顔』
『朝顔』の意味
夏から秋にかけて咲く花で、
朝に開き昼にはしぼむ姿が特徴。
古くから観賞用として親しまれ、
江戸時代には栽培が盛んに行われました。
秋の植物季語として、
はかなさと季節の移ろいを伝えます。
『朝顔』のコラム
朝顔は「はかなきもの」の象徴として、
恋や人生の無常を重ねて詠まれました。
花が短命であることから、
一瞬の輝きや儚い出会いを表現。
鮮やかな花色と対照的に、
余情を残す季語として愛されます。
『朝顔』の例句をご紹介
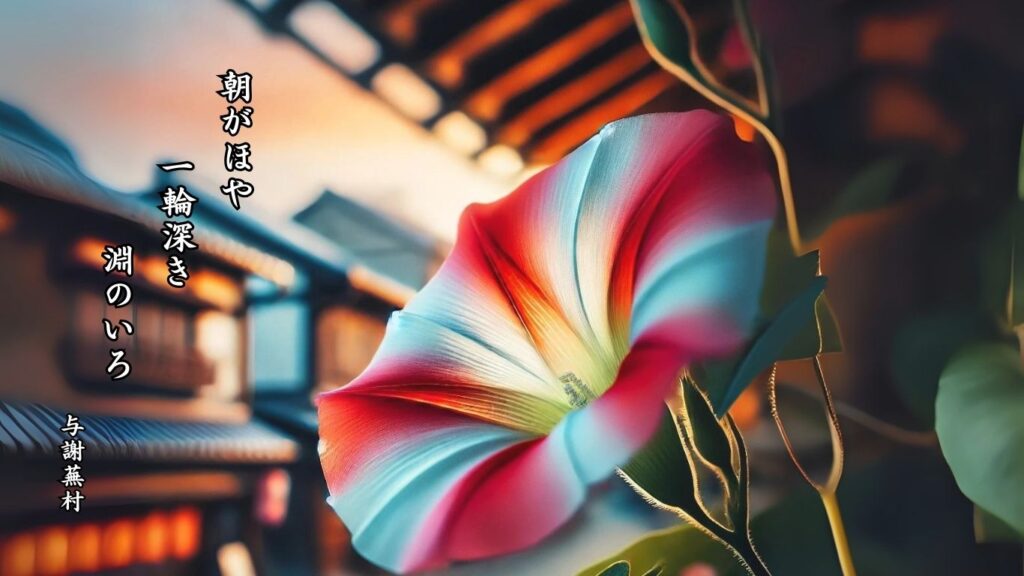
俳句:朝がほや 一輪深き 淵のいろ
読み:あさがおや いちりんふかき ふちのいろ
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:一輪の朝顔の色を、
深い淵の色に重ね合わせている。
花の清らかさと水の深みが響き合い、
自然の奥行きと静けさを表現。
蕪村らしい繊細な比喩が光る
情緒豊かな一句です。
季語『鳳仙花』
『鳳仙花』の意味
夏から秋にかけて咲く一年草で、
紅や紫の花をつけ、実が熟すと
はじけて種を飛ばすのが特徴です。
日本では古くから庭先で親しまれ、
子どもたちが花をつんで遊ぶなど、
身近な秋の植物季語とされます。
『鳳仙花』のコラム
鳳仙花は、種のはじける様子から、
別れやはかなさを詠む題材となりました。
鮮やかな花色は華やかさを添えつつ、
どこか哀愁を漂わせます。
俳句では童心や郷愁を呼び起こす、
親しみ深い季語として愛されています。
『鳳仙花』の例句をご紹介

俳句:汲み去つて 井辺しずまりぬ 鳳仙花
読み:くみさって いべしずまりぬ ほうせんか
俳人名:原石鼎 (はら せきてい)
要約:水を汲み終え、
人影が去った井戸端に
静けさが戻る。
そこに咲く鳳仙花がひときわ映え、
日常の営みと自然の美が調和する。
静と動の対比が印象的な
石鼎らしい一句です。
季語『菊』
『菊』の意味
古来より日本を代表する花で、
秋を象徴する植物季語です。
長寿や不老不死の象徴とされ、
重陽の節句では邪気を払う花として
用いられました。
多彩な花色と姿で人々に親しまれ、
今も秋の風物詩として愛されています。
『菊』のコラム
菊は気高く凛とした花姿から、
清らかさや高貴さを表す題材となりました。
俳句では白菊の静けさや、
黄菊の明るさなど、
色彩の違いを生かして詠まれることが多く、
季節の深まりとともに余情を伝えます。
『菊』の例句をご紹介

俳句:白菊の 目に立てて見る 塵もなし
読み:しらぎくの めにたててみる ちりもなし
俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)
→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと
要約:白菊を見つめると、
塵ひとつ見えない清浄な世界が広がる。
花の純白さが心を洗い、
自然の美と精神の澄みを重ねる。
芭蕉らしい簡潔さと深い余韻を持つ
象徴的な一句です。
季語『紅葉』
『紅葉』の意味
秋の冷え込みとともに葉が色づき、
赤や黄に山野を染める現象を指します。
古来より和歌や俳句に詠まれ、
四季の中でも特に人々を魅了する景色です。
日本文化に深く根づき、
秋を代表する植物季語とされています。
『紅葉』のコラム
紅葉は、華やかさのなかに
もののあわれを感じさせる題材です。
鮮やかな彩りは命の盛りを示すとともに、
散りゆく運命を暗示します。
俳句では光や風との対比で詠まれ、
深い余情を残す季語として親しまれます。
『紅葉』の例句をご紹介

俳句:障子しめて 四方の紅葉を 感じをり
読み:しょうじしめて しほうのもみじを かんじをり
俳人名:星野立子 (ほしの たつこ)
要約:障子を閉めてもなお、
四方から紅葉の気配が満ちてくる。
視覚を超えて季節が伝わる様子に、
自然の力強さと感性の豊かさが重なる。
立子らしい繊細な感覚を映した
一句です。
季語『照葉』
『照葉』の意味
秋の深まりとともに
木の葉が色づき、
陽光や月光を受けて
照り映える様子を指します。
赤や黄に輝く葉は
自然の彩りを際立たせ、
山野の景観を豊かにします。
静かな光を宿す姿は、
秋の成熟を示す植物季語です。
『照葉』のコラム
照葉は、光に映える葉の美しさから、
人生の円熟や豊かさに例えられました。
また、照葉峡など名所も多く、
旅や風景詠の題材として親しまれます。
俳句では紅葉と並んで詠まれ、
静けさや余韻を深める季語です。
『照葉』の例句をご紹介
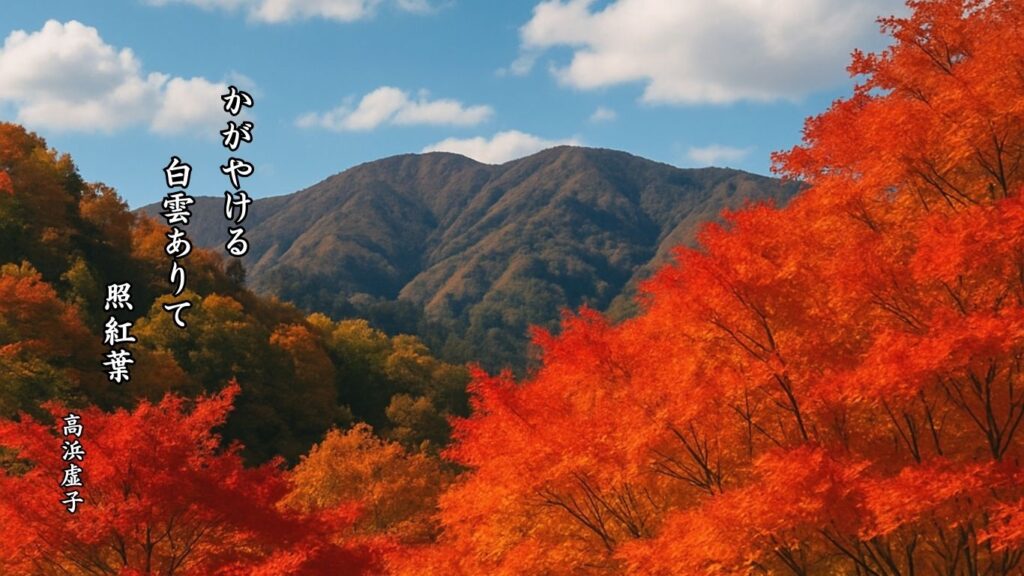
俳句:かがやける 白雲ありて 照紅葉
読み:かがやける しらくもありて てりもみじ
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:輝く白雲と照り映える紅葉が、
秋空に鮮やかな対比を生む。
光と色彩の調和が力強く、
自然の壮大な美を伝える。
虚子らしい明快で華やかな描写が
印象深い一句です。
季語『鬼灯』
『鬼灯』の意味
夏から秋にかけて赤く色づく実を
提灯に見立てたことから
名づけられました。
透けるような赤い果皮の中に、
小さな実を包む姿が特徴です。
観賞用や盆飾りとしても親しまれ、
秋を象徴する植物季語となりました。
『鬼灯』のコラム
鬼灯は、赤く灯るような実から、
生と死をつなぐ象徴とされてきました。
盆には霊を導く灯として飾られ、
俳句では郷愁や哀愁を込めて詠まれます。
童心や懐かしい情景を呼び起こす、
印象深い秋の季語です。
『鬼灯』の例句をご紹介

俳句:鬼灯や 物うちかこつ 口のうち
読み:ほおずきや ものうちかこつ くちのうち
俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)
→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと
要約:鬼灯を口に含み鳴らしながら、
ものを言い募る人の姿を描く。
子どもの遊びや大人の愚痴を重ね、
鬼灯の素朴さと人間味がにじむ。
太祇らしいユーモアと生活感に
彩られた一句です。
季語『秋草』
『秋草』の意味
秋に野原を彩る草花の総称で、
萩・芒・桔梗などを含みます。
古来より「秋の七草」として親しまれ、
和歌や俳句にも数多く詠まれました。
野に咲く素朴な花々は、
季節の移ろいを象徴する
代表的な植物季語です。
『秋草』のコラム
秋草は、華やかさよりも
さりげない風情が重んじられ、
人の心に寄り添う存在として
詩歌に登場します。
野辺に広がる群れ咲きの景色は、
はかなさと調和を伝え、
静かな余情を残す季語です。
『秋草』の例句をご紹介
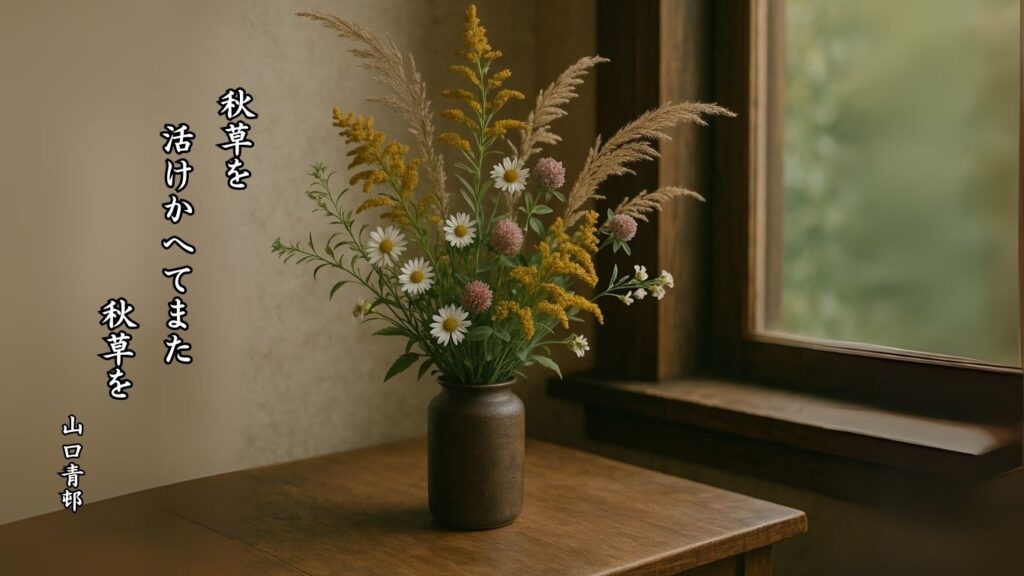
俳句:秋草を 活けかへてまた 秋草を
読み:あきくさを いけかえてまた あきくさを
俳人名:山口青邨 (やまぐち せいそん)
→ことばあそびの詩唄で青邨の句をもっと
要約:秋草を活け替えても、
また新たに秋草を生ける。
尽きぬ花の美と人の営みが重なり、
季節の豊かさを映す。
日常の中に自然を取り入れる
日本的な感性を捉えた一句です。
季語『撫子』
『撫子』の意味
秋に咲く可憐な花で、
細やかな花びらが
風に揺れる姿が特徴です。
その名は
「なでしこ=愛らしい子」に由来し、
古くから親しまれました。
秋の七草のひとつとして数えられ、
和歌や俳句にも盛んに詠まれる
代表的な植物季語です。
『撫子』のコラム
撫子はその可憐な姿から、
純真さや愛らしさの象徴とされました。
恋の歌や子を思う心を重ね、
和歌・俳句に詠まれてきました。
野にひっそりと咲く姿は、
はかなさと清らかさを漂わせ、
余情ある季語として親しまれます。
『撫子』の例句をご紹介

俳句:酔うて寝む なでしこ咲ける 石の上
読み:ようてねむ なでしこさける いしのうえ
俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)
→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと
要約:酔って石の上に寝ようとすると、
そこには撫子の花が咲いている。
人の滑稽な行為と
花の可憐さが響き合い、
自然と生活の交錯を軽妙に描く。
芭蕉らしい洒脱な
感性が光る一句です。
季語『桔梗』
『桔梗』の意味
秋の七草のひとつで、
青紫の星形の花を咲かせます。
古くから薬草としても知られ、
その根は生薬として用いられました。
清楚で気品ある姿から、
和歌や俳句に多く詠まれ、
秋を代表する植物季語とされます。
『桔梗』のコラム
桔梗は凛とした花姿から、
誠実や変わらぬ心を象徴します。
武家の家紋にも用いられ、
高貴な印象を持ちました。
俳句では秋の澄んだ空と響き合い、
静けさや清らかさを伝える
余情ある季語として親しまれます。
『桔梗』の例句をご紹介
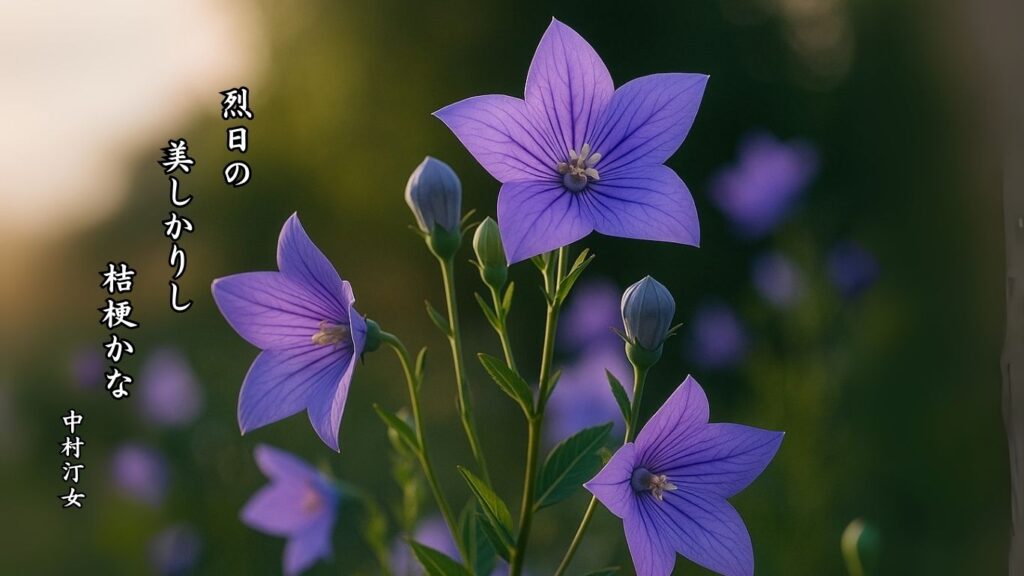
俳句:烈日の 美しかりし 桔梗かな
読み:れつじつの うつくしかりし ききょうかな
俳人名:中村汀女 (なかむら ていじょ)
→ことばあそびの詩唄で汀女の句をもっと
要約:烈日の光を浴びても、
なお美しさを保つ桔梗の花。
強さと清らかさが同居し、
夏の厳しさから秋への移ろいを示す。
自然の逞しさと繊細さを映す、
汀女らしい観察眼の一句です。
季語『女郎花』
『女郎花』の意味
秋の七草のひとつで、
細かな黄色の花を房状につけます。
その名は、女性の優雅さに由来し、
古くから歌に詠まれてきました。
野に群れて咲く姿は華やかで、
秋の野を彩る代表的な植物季語です。
『女郎花』のコラム
女郎花は、そのしなやかな姿から、
はかなさや哀愁を表現する題材として
和歌や俳句に親しまれました。
他の秋草とともに群生する景観は、
調和や移ろいを感じさせます。
古典文学にも多く登場する、
風雅な季語です。
『女郎花』の例句をご紹介

俳句:手折りては はなはだ長し 女郎花
読み:たおりては はなはだながし おみなえし
俳人名:炭太祇 (たん たいぎ)
→ことばあそびの詩唄で太祇の句をもっと
要約:手折った女郎花が、
意外なほど長く伸びている。
素朴な驚きの中に、
秋草のしなやかさと優美さが漂う。
自然の細やかな美に目を向けた、
太祇らしい写生の一句です。
季語『萩』
『萩』の意味
秋の七草の代表であり、
小さな赤紫の花を
枝いっぱいに咲かせます。
風にそよぐ姿は優雅で、
万葉集以来、
多くの歌に詠まれました。
秋の草花の象徴として親しまれ、
古来より日本の風景に深く根づく
代表的な植物季語です。
『萩』のコラム
萩は、風に揺れる繊細な姿から、
はかなさや移ろいを象徴します。
夕暮れや月明かりのもとでの情景は、
和歌や俳句に多く描かれました。
秋の野を彩る群生は、
豊かさと寂しさをあわせ持ち、
余情深い季語として親しまれます。
『萩』の例句をご紹介

俳句:高くあげて 提灯越ゆる 萩むらを
読み:たかくあげて ちょうちんこゆる はぎむらを
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:提灯を高く掲げ、
萩の群れを越えて進む。
秋の夜の行事と自然が溶け合い、
光と草花が織りなす情景が広がる。
人と季節の調和を描いた、
虚子らしい写生の一句です。
季語『芒』
『芒』の意味
秋の七草のひとつで、
細長い葉と白い穂を風に揺らします。
「すすき」とも呼ばれ、
月見の飾りにも用いられます。
古くから秋の野を象徴する植物であり、
野原を銀色に染める姿は、
秋の代表的な植物季語です。
『芒』のコラム
芒は、風や光を受けて揺れる姿から、
寂寥感や静けさを
表現する題材となりました。
月や虫の声と取り合わせて詠まれ、
秋の情緒を深めます。
その素朴で力強い姿は、
自然と調和する美を象徴する
親しまれた季語です。
『芒』の例句をご紹介
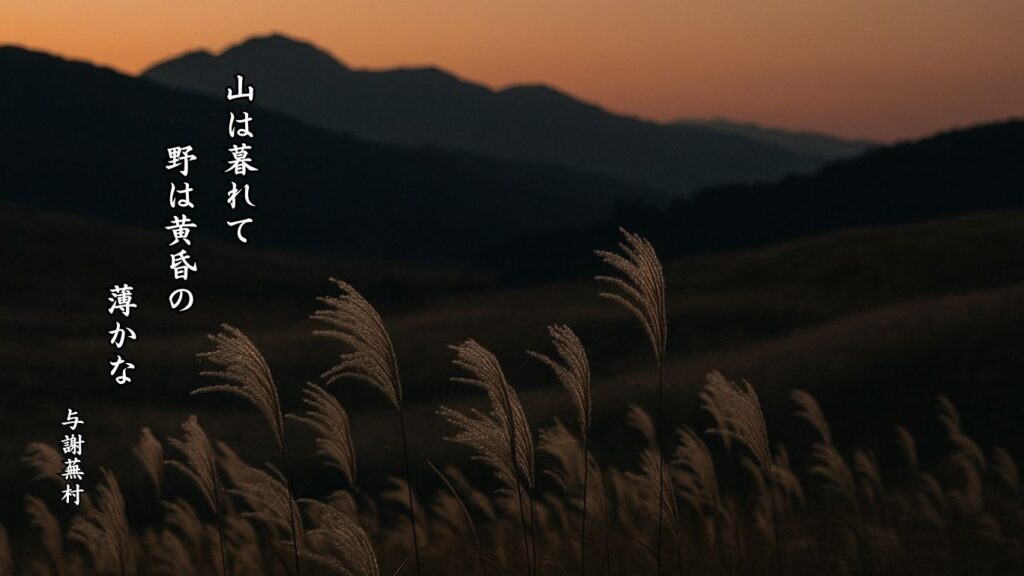
俳句:山は暮れて 野は黄昏の 薄かな
読み:やまはくれて のはたそがれの すすきかな
俳人名:与謝蕪村 (よさ ぶそん)
→ことばあそびの詩唄で蕪村の句をもっと
要約:山は暮れ、野は黄昏に包まれる。
その中に立つ薄が静かに揺れ、
秋の夕景の寂寥を際立たせる。
自然の移ろいを繊細にとらえた、
蕪村らしい余情豊かな一句です。
まとめ
秋の植物季語は、萩や芒、菊など
四季の中でも彩り豊かな情景を映します。
古くから俳句や和歌に詠まれ、
はかなさや余情を伝える言葉として
今も私たちの心に寄り添う
代表的な秋のことばです。
関連リンク
📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)
🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る
🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら