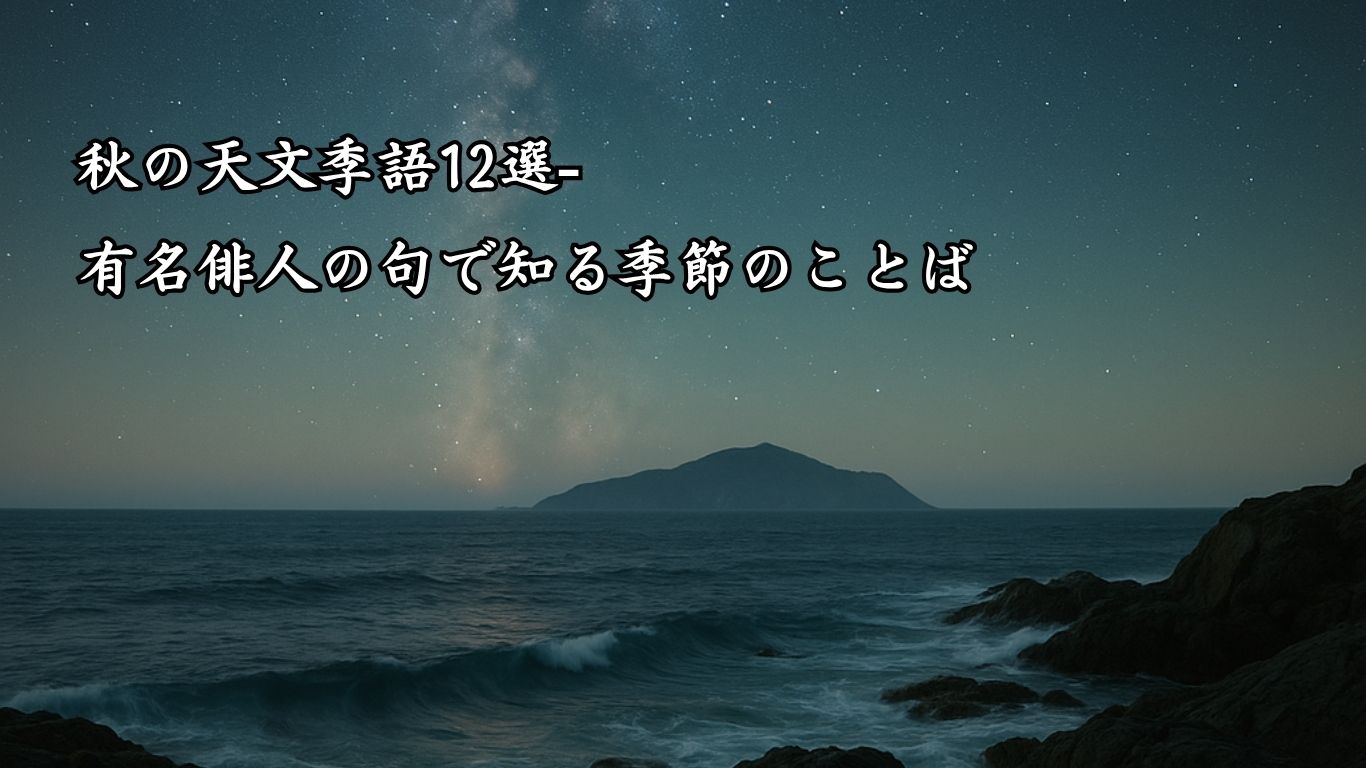秋に触れる、やさしい季語たち
澄んだ空に月や星が輝く、
秋の夜空は格別の美しさです。
今回は「秋の天文季語」から
代表的な12語をご紹介。
有名俳人の句とともに、
夜空に映る季節の表情を
やさしく味わってみましょう。
秋の天文季語12選
秋の天文季語『台風』
『台風』の意味
台風は熱帯低気圧の一種で、
強い風雨を伴って日本列島に接近します。
秋は台風の発生が多く、
稲刈りや秋祭りの時期とも重なり、
暮らしや風景に影響を与える
代表的な天文季語です。
『台風』のコラム
俳句では、台風の前後の空や海、
風や雨の勢いなどが詠まれます。
被害や不安を描く句もあれば、
通過後の静けさをとらえた句も。
自然の力と人の営みの関係を
鮮やかに映す季語です。
『台風』の例句をご紹介

俳句:台風に 吹かれ吹かれつ 投函す
読み:たいふうに ふかれふかれつ とうかんす
俳人名:石田波郷 (いしだ はきょう)
→ことばあそびの詩唄で波郷の句をもっと
要約:強い風雨にあおられながらも、
懸命に郵便を投函する姿を描く一句。
台風という自然の力と、
日常の営みが交差する瞬間に、
人のたくましさと季節感がにじみます。
秋の天文季語『秋風』
『秋風』の意味
夏の暑さがやわらぎ、
涼しさを含んだ風を「秋風」といいます。
空気が澄み、肌をすべるような感覚や、
草木を揺らす音などで
季節の移ろいを感じさせる、
代表的な秋の天文季語です。
『秋風』のコラム
俳句では、
秋風は爽やかさだけでなく、
物寂しさや感傷を
ともなう表現にも使われます。
古典から現代まで幅広く詠まれ、
心の変化や旅情、別れなど、
人の情感と重ねて描かれる
奥行きのある季語です。
『秋風』の例句をご紹介
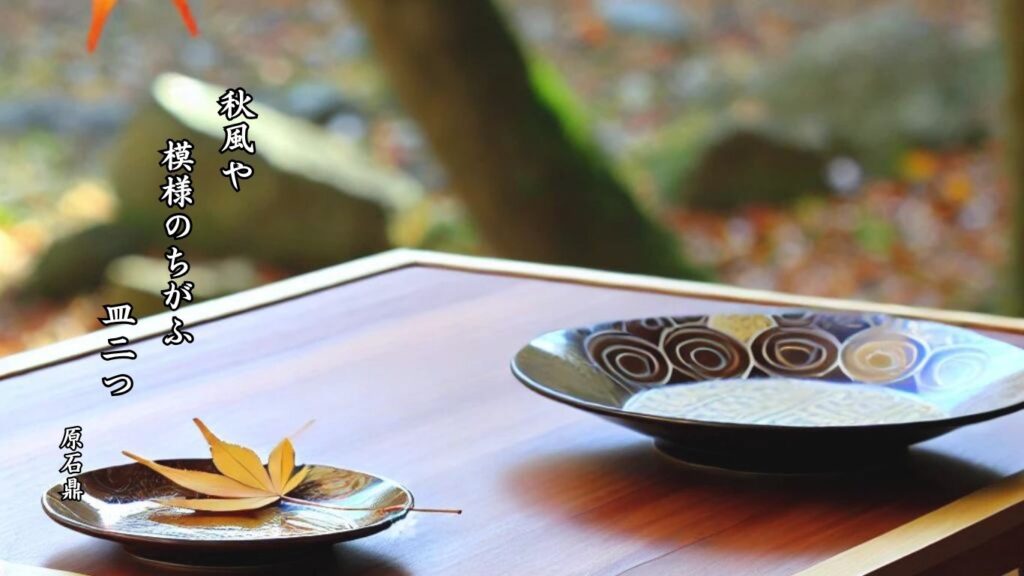
俳句:秋風や 模様のちがふ 皿二つ
読み:あきかぜや もようのちがう さらふたつ
俳人名:原石鼎 (はら せきてい)
要約:模様の異なる皿が二枚並ぶ光景に、
秋風がそっと吹き抜ける。
何気ない日常の一場面に、
季節の涼しさと静けさを重ね、
しみじみとした情緒を漂わせています。
秋の天文季語『秋の空』
『秋の空』の意味
澄みきった青さや、
高く広がる空を指す季語です。
空気が乾き、遠くまで見渡せる秋は、
一年で最も空が美しい季節。
一方で天気が変わりやすく、
移ろう空模様もまた
秋の特徴として親しまれています。
『秋の空』のコラム
俳句では澄んだ青空や、
流れる雲の情景がよく詠まれます。
爽やかな開放感を表す句もあれば、
物寂しさや無常感を映す句も。
空の高さや光の加減など、
視覚的な美しさと心情を
同時に描ける奥行きある季語です。
『秋の空』の例句をご紹介
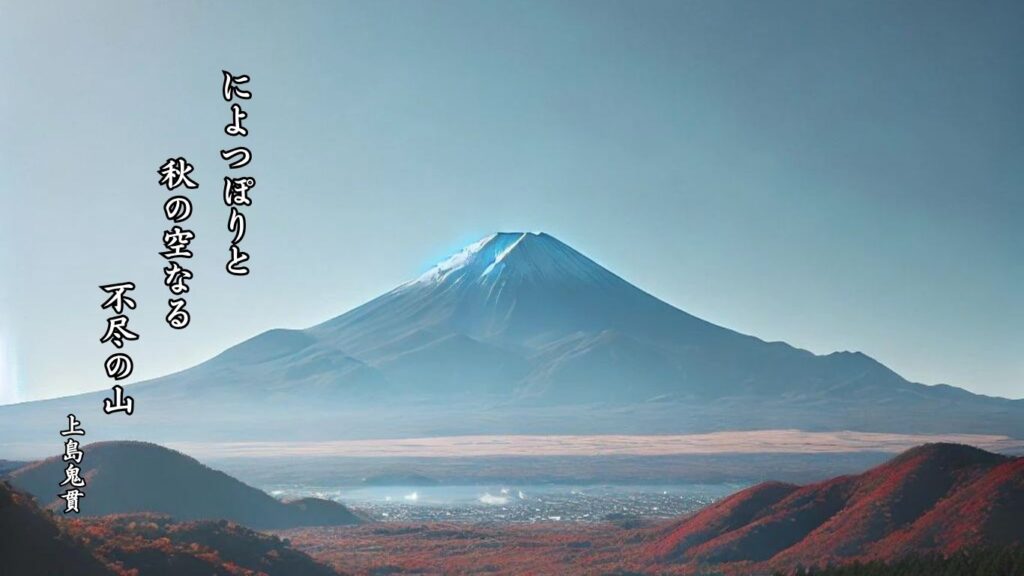
俳句:によつぽりと 秋の空なる 不尽の山
読み:によっぽりと あきのそらなる ふじのやま
俳人名:上島鬼貫 (うえじま おにつら)
要約:澄み渡る秋の空のもと、
富士山がのびやかに姿を見せる情景。
「によっぽりと」という表現が、
自然の雄大さと人の感嘆を軽やかに伝え、
秋空の爽快感を際立たせています。
秋の天文季語『天高し』
『天高し』の意味
秋の空が澄み渡り、
高く広がって見える様子を表す季語です。
空気が乾き、雲がくっきりと浮かぶ秋は、
一年で最も空が高く感じられる季節。
爽快さや解放感を伴い、
俳句でも人気の高い表現です。
『天高し』のコラム
「天高し」は視覚的な
爽やかさだけでなく、
豊穣や実りの季節を象徴します。
田畑や山の景色と
組み合わせて詠まれるほか、
旅や人生の広がりを重ねる句も。
秋の開放感と希望を込めた
明るい季語として親しまれています。
『天高し』の例句をご紹介
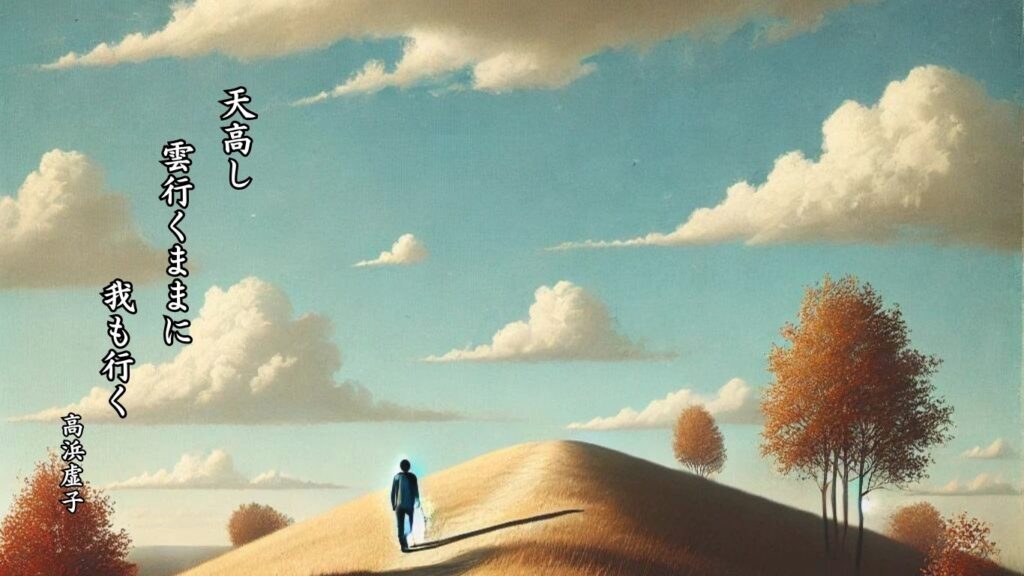
俳句:天高し 雲行くままに 我も行く
読み:てんたかし くもゆくままに われもゆく
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:澄み渡る秋空に漂う雲のように、
自分も流れのままに歩んでいく。
「天高し」の爽快感と、
人生を軽やかに受け入れる姿勢が重なり、
自由な心を感じさせる一句です。
秋の天文季語『秋時雨』
『秋時雨』の意味
晩秋から初冬にかけて、
降ったかと思えばすぐに止む、
そんな通り雨を「秋時雨」といいます。
冷たさを含む雨は、
季節の移ろいを告げるように
静かに降り、景色に
寂しさや風情を添える季語です。
『秋時雨』のコラム
俳句では、秋時雨は色や音の描写と
結びつくことが多く、
紅葉や枯葉、町並みなどを
しっとりと濡らす情景に詠まれます。
冬の「時雨」に比べてやわらかく、
秋らしい静けさと余情を
感じさせる表現です。
『秋時雨』の例句をご紹介
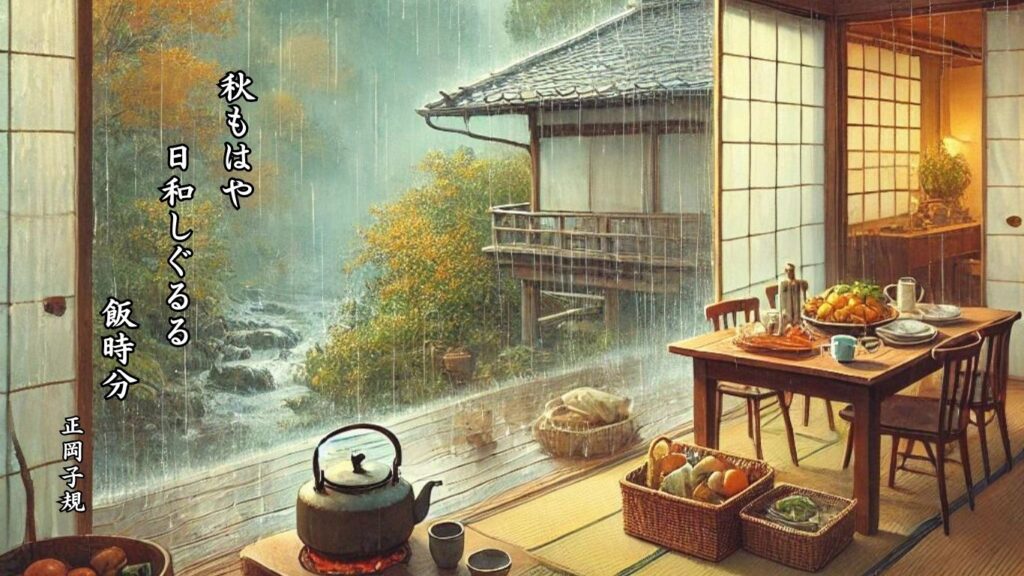
俳句:秋もはや 日和しぐるる 飯時分
読み:あきもはや ひよりしぐるる めしじぶん
俳人名:正岡子規 (まさおか しき)
→ことばあそびの詩唄で子規の句をもっと
要約:秋も深まり、
食事のころにふと降る秋時雨。
日常のひとこまに
季節の移ろいが溶け込み、
静かな情緒と時間のぬくもりを
感じさせる一句です。
秋の天文季語『名月』
『名月』の意味
旧暦八月十五夜の満月を
「名月」と呼びます。
一年で最も美しいとされ、
澄んだ秋空に冴え冴えと輝きます。
観月の風習と結びつき、
俳句では月の光や
夜の情緒を表す
代表的な天文季語です。
『名月』のコラム
名月は「中秋の名月」とも呼ばれ、
古くから月見の宴や
詩歌に親しまれました。
俳句では光や影の描写だけでなく、
心情や人生観と
重ねて詠まれることも多く、
秋夜の象徴として広く用いられます。
『名月』の例句をご紹介
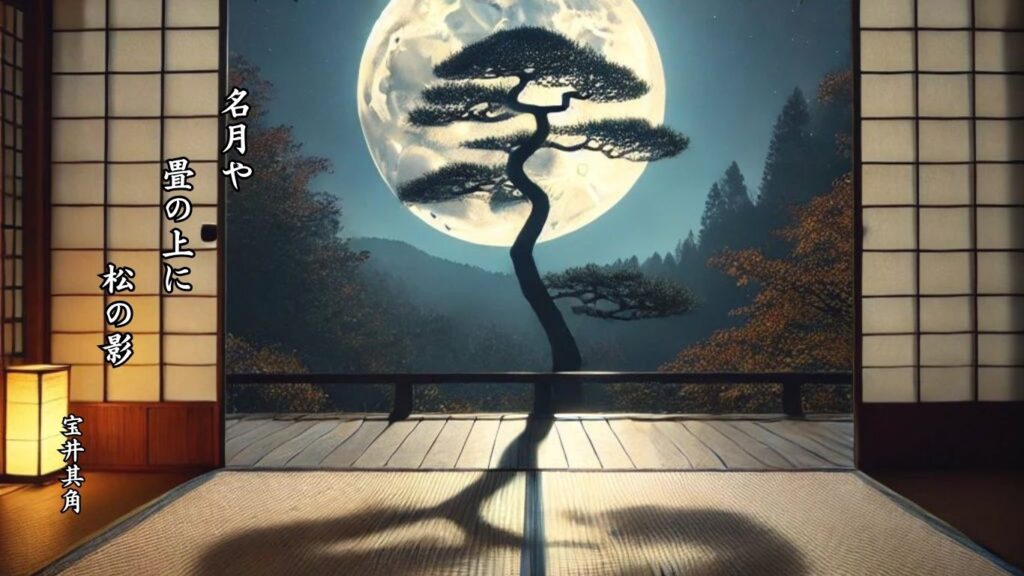
俳句:名月や 畳の上に 松の影
読み:めいげつや たたみのうえに まつのかげ
俳人名:宝井其角 (たからい きかく)
→ことばあそびの詩唄で其角の句をもっと
要約:名月の光が畳に松の影を落とす。
屋内にいながら
月夜の美を味わう情景で、
自然と人の暮らしが
静かに溶け合い、
秋夜の風雅が際立つ一句です。
秋の天文季語『萩の声』
『萩の声』の意味
風に揺れる萩の花に、
虫の音が重なって聞こえる様子を
「萩の声」といいます。
目で見る花の姿と、
耳で感じる秋の音色が一体となり、
季節の深まりを伝える
感覚的な天文季語です。
『萩の声』のコラム
俳句では、萩の花と虫の声を
組み合わせた描写が多く、
秋の夜や夕暮れの情景に詠まれます。
視覚と聴覚を同時に刺激し、
静けさや余情を表現できるため、
古くから愛される情緒豊かな季語です。
『萩の声』の例句をご紹介

俳句:萩吹くや 葉山通ひの 仕舞馬車
読み:おぎふくや はやまがよいの しまいばしゃ
俳人名:高浜虚子 (たかはま きょし)
→ことばあそびの詩唄で虚子の句をもっと
要約:萩を揺らす風の中、
葉山通いの最後の馬車が走る。
視覚と聴覚が交わる情景に、
季節の終わりの寂しさと、
秋らしい余情がにじむ一句です。
秋の天文季語『初嵐』
『初嵐』の意味
秋になって初めて吹く
強い風を「初嵐」といいます。
夏から秋への季節の変わり目に現れ、
木々や波を揺らす力強さと、
空気の冷たさを伴います。
季節の節目を告げる
天文季語です。
『初嵐』のコラム
俳句では、初嵐は自然の迫力や、
変化の予感を描く表現として好まれます。
海辺や山間の情景と結びつくことが多く、
音や動きで秋の訪れを印象づけます。
旅や別れの句にも使われる
季節感豊かな言葉です。
『初嵐』の例句をご紹介
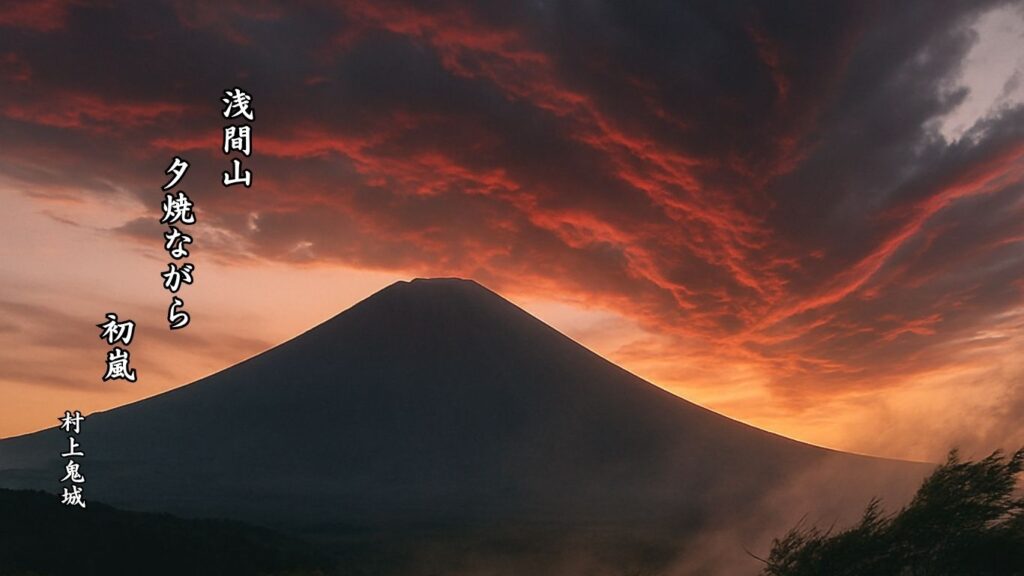
俳句:浅間山 夕焼ながら 初嵐
読み:あさまやま ゆうやけながら はつあらし
俳人名:村上鬼城 (むらかみ きじょう)
要約:夕焼けに染まる浅間山に、
秋の初嵐が吹き渡る。
雄大な自然と力強い風の動きが重なり、
季節の変わり目の迫力と
美しさを同時に描いた一句です。
秋の天文季語『天の川』
『天の川』の意味
夜空に白く流れるように見える
星の帯を「天の川」といいます。
無数の星が集まって輝き、
秋は空気が澄んで
いちばん美しく観賞できます。
七夕伝説や詩歌とも深く結びつく
天文季語です。
『天の川』のコラム
俳句では、
天の川は静寂や広がり、
時の流れを感じさせる
題材として好まれます。
川に見立てた流れや、
人の思いを星に託す表現も多く、
浪漫的で幻想的な秋の夜空を
象徴する季語です。
『天の川』の例句をご紹介
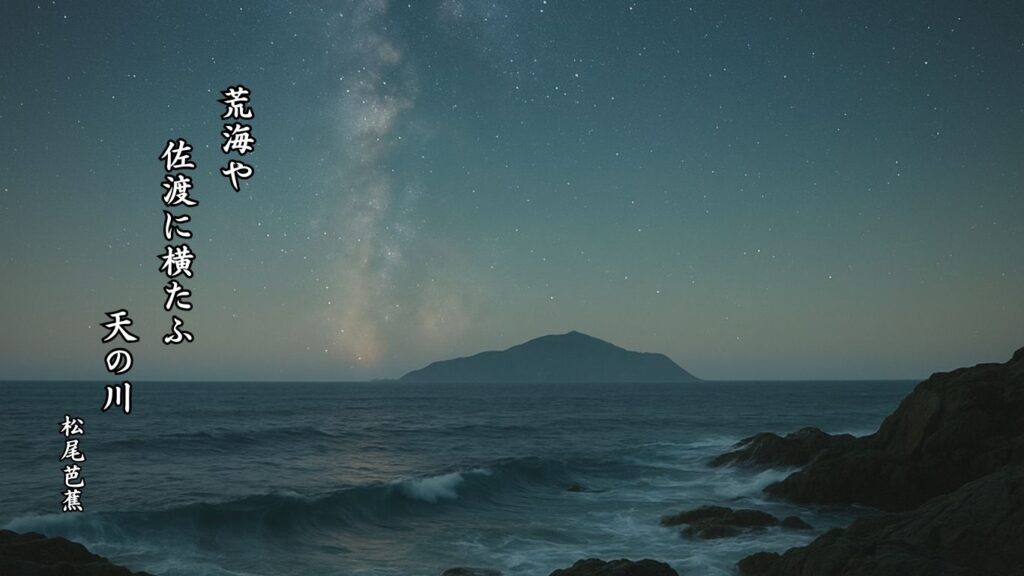
俳句:荒海や 佐渡に横たふ 天の川
読み:あらうみや さどによこたう あまのがわ
俳人名:松尾芭蕉 (まつお ばしょう)
→ことばあそびの詩唄で芭蕉の句をもっと
要約:荒々しい海の向こうに、
佐渡島が横たわり、その上に
天の川が架かる壮大な光景。
海と空、現実と幻想が溶け合い、
自然のスケールの大きさを
感じさせる一句です。
秋の天文季語『星月夜』
『星月夜』の意味
澄みきった空に星が冴え冴えと輝く
秋の夜を「星月夜」といいます。
月の光と星の輝きが同時に見られ、
空気の透明感や静けさが際立つ季節。
夜空の美を象徴する
秋ならではの天文季語です。
『星月夜』のコラム
俳句では、
星月夜は光の明暗や
夜の静けさを描く
題材として好まれます。
旅や人生の情景に重ねたり、
孤独や感傷を映す句も多く、
視覚的な美しさと心情表現を
兼ね備えた奥行きある季語です。
『星月夜』の例句をご紹介
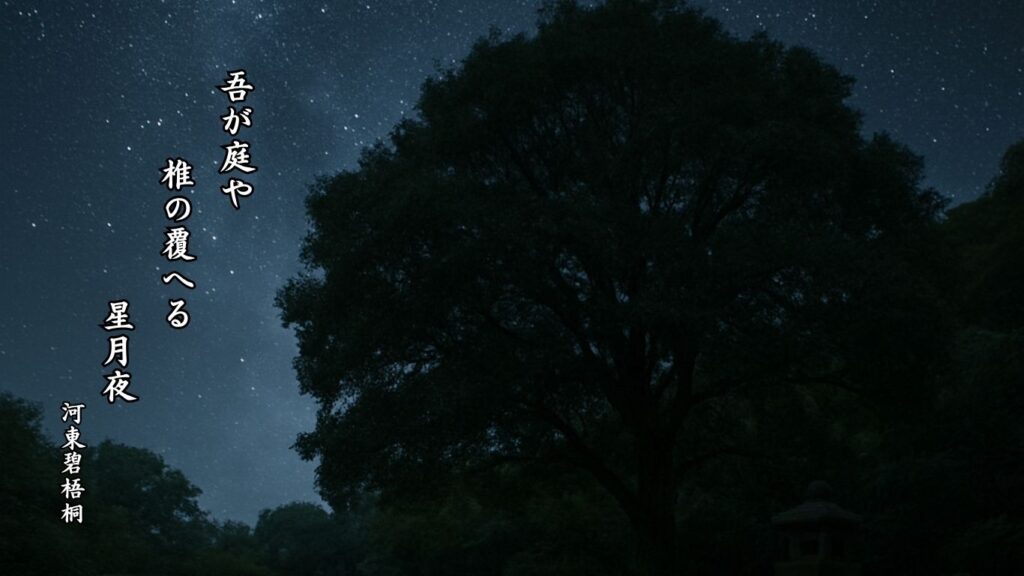
俳句:吾が庭や 椎の覆へる 星月夜
読み:わがにわや しいのおおえる ほしづきよ
俳人名:河東碧梧桐 (かわひがし へきごとう)
→ことばあそびの詩唄で碧梧桐の句をもっと
要約:自分の庭を覆う椎の木の向こうに、
星が冴え冴えと輝く秋の夜。
身近な空間に広がる宇宙の美しさと、
星月夜の静けさが溶け合う、
しみじみとした情景の一句です。
秋の天文季語『流星』
『流星』の意味
夜空を流れる光の筋を
「流星」といいます。
小さな塵が大気に燃えて輝き、
一瞬で消える様子は儚く美しい。
秋は空気が澄み、
観測に適した季節で、
願い事をかける風習でも
親しまれる天文季語です。
『流星』のコラム
俳句では、流星は時間の速さや
人生の儚さの象徴として詠まれます。
夏のペルセウス座流星群に対し、
秋はオリオン座流星群が有名。
動きや光跡の描写を通して、
感動や余情を表す句が多く
残されています。
『流星』の例句をご紹介
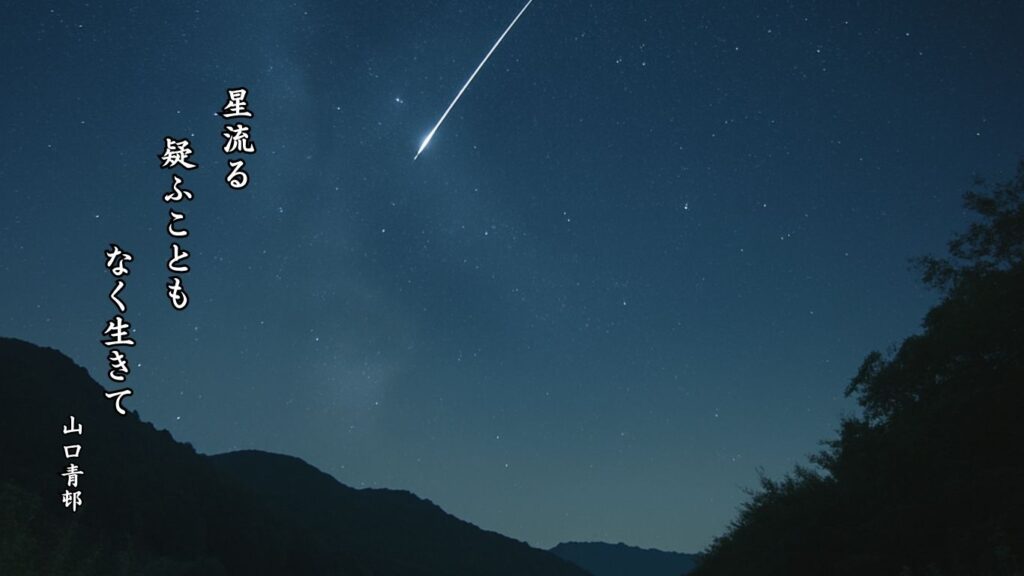
俳句:星流る 疑ふことも なく生きて
読み:ほしながる うたがうことも なくいきて
俳人名:山口青邨 (やまぐち せいそん)
→ことばあそびの詩唄で青邨の句をもっと
要約:夜空を流れる星を見つめ、
疑うことなく生きてきた日々を思う。
流星の潔い光跡に、
揺るぎない人生観と静かな感慨が
重なり合う一句です。
秋の天文季語『盆の月』
『盆の月』の意味
旧暦七月十五日の夜、
お盆の行事とともに眺める月を
「盆の月」といいます。
先祖の霊を迎える時期の月は、
静かで優しい光を放ち、
家族や故郷の情景と結びつく
秋の天文季語です。
『盆の月』のコラム
俳句では、盆の月は追憶や郷愁を
表す題材として好まれます。
川辺や山里の景とともに描かれ、
先祖とのつながりや心の安らぎを
感じさせる表現が多いです。
そのやわらかな光は、
夏と秋の境目を彩ります。
『盆の月』の例句をご紹介
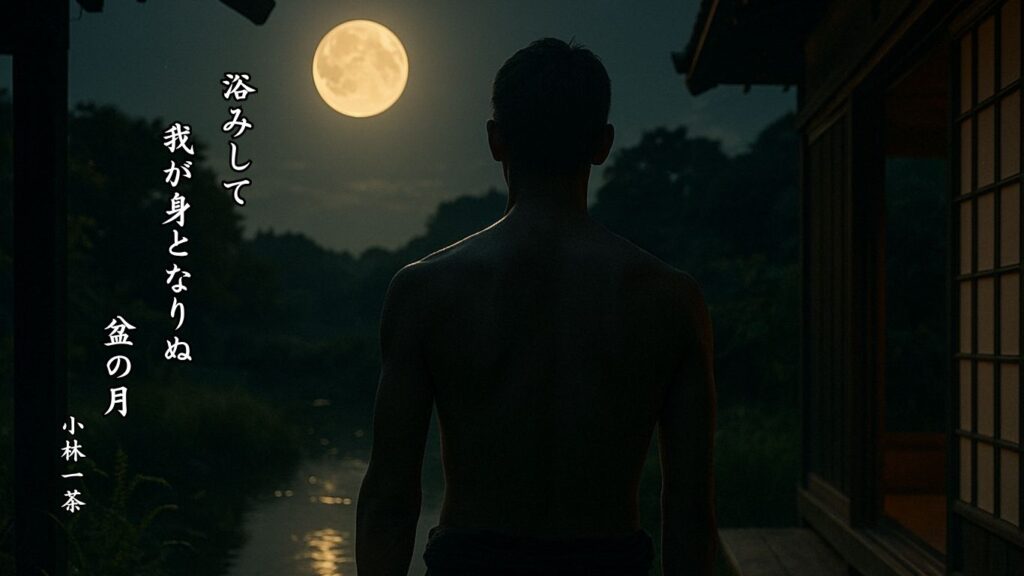
俳句:浴みして 我が身となりぬ 盆の月
読み:ゆあみして わがみとなりぬ ぼんのつき
俳人名:小林一茶 (こばやし いっさ)
→ことばあそびの詩唄で一茶の句をもっと
要約:湯浴みを終えた自分の体に、
盆の月の光がやさしく差し込む。
清められた心身と
月の静かな輝きが重なり、
お盆ならではの安らぎと
秋の情緒を感じさせる一句です。
まとめ
秋の天文季語は、
夜空や自然の表情を映す
豊かなことばです。
俳人の句にふれながら、
月や星、風や空の移ろいを
心に留めてみてください。
季節の美しさが
一層深まります。
関連リンク
📷 Instagramアカウントへ(@HaikuEchoes_575)
🏡 わたぼうし詩小径トップへ戻る
🪷 ことばあそびの詩唄 メインサイトはこちら